- ホーム
- RSYブログ
RSYブログ
睡眠夫妻
2020/09/08
こんにちは。外の雰囲気がどんどん秋になってきました。過ごしやすい季節ですよね。気力、体力が充実します。
そしてその気力と体力を毎日回復させる一番の充電器が睡眠です。睡眠は大事。誰もが大事だとわかっていると思います。
でもついついやってしまうんですよね。睡眠不足。僕も最近まで作業に追われてやってしまいました。睡眠時間を削るという行為。なかなか仕事が終わらないと夜中まで持ち込みがちです。
でもそんな生活が続いてみるとわかることですが、完全に効率が悪い。睡眠が一日でも不足すると次の日の集中力が落ち活動がパワーダウン、結局作業効率が落ちます。ダラダラと時間の使い方ヘタになります。午前中の作業がなあなあ。お昼ご飯を食べた後も集中できない。結局夜に仕事を持ち越し。そんなサイクルに陥ってしまいます。
「睡眠負債」なんていう言葉も生まれるくらいですから多くの人がそんな生活を送ってるのかもしれません。
結局睡眠が適正にとれた時の朝の1時間の作業の方が、睡眠不足の日の夜の4時間よりも捗るのです。ミスも少ない。これは自分で仕事をしている人も会社勤めの人も家事をしている人も同じですね。
なのでまず睡眠。睡眠=集中力=時間の効率的な使い方。これを頭に入れておきます。(僕も自分に言い聞かせてます笑)
ただ人によって睡眠の適正時間は全然違うようなので注意が必要です。中には睡眠時間が3〜4時間くらいで済むショートスリーパーの方もいます。8時間前後必要な方もいます。その辺りは大方遺伝で決まるようなので自分の基準を見つけることが大切です。(瞑想で睡眠時間を短くすることはできますが、8時間→3時間にすることは難しいでしょう。)
睡眠不足の方はぜひ自分の生活を見つめ直してどうやったら時間を効率的に使えるかを考えてみるといいかもしれません。時間=命ですからね。
逆に寝過ぎで気力が失われているパターンについてはまたそのうち。いずれにしても一定の量の睡眠と質が大切ですね。
瞳をとじて太陽を拝むよ
2020/09/07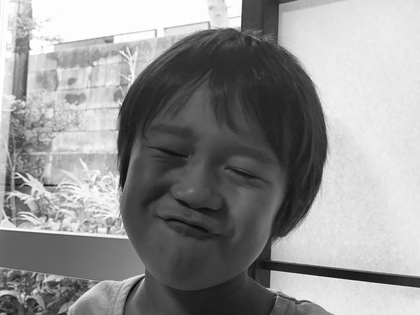
台風の影響で強い雨が降ったり止んだりすごい天気ですね。東京は雨くらいで大丈夫ですが九州の方にお住まいの方はお気をつけくださいね。2年前に宮古島で経験した台風はものすごかったです。毎年来るものでも全く油断できないですよね。
さて、今日の朝もいつも通り瞑想やプラーナヤーマを行った後にアーサナで動こうと思ったのですが、どうもこの低気圧でやる気が起きない。脳髄液ももろに停滞している感じです。なのでずっと瞑想やプラーナヤーマを行っていようかなとも思ったのですが、少しでも動いた方が後々の調子は良くなることがわかっていました。
そこで、、
目を閉じて動いてみよう!
と思いつきました。
そして目を閉じての太陽礼拝。やはり良い感触。元々太陽礼拝では視線を定めることが大事なのですが、台風の日はとにかく目もつらい。なので瞼を閉じていると目が休まり楽です。しかも予想通り瞑想状態に入りやすいのです。
最近は座りの瞑想がだんだん上達してきて、座ってからすぐに瞑想状態に入れるようになっていたのですが、目を閉じると太陽礼拝でも座りの瞑想に近い状態に入れます。視覚に頼れない分少しフラフラしますが、バランス感覚を鍛えるのには良いかなと思いました。
ジャンプインなどで足を浮かせる際は薄目を開けていましたが。。
目を閉じての練習はいつもと違う発見があるので太陽礼拝を普段からやっている方は試してみるとおもしろいかもしれません。でもバランス崩して転倒しないように十分にお気をつけくださいね。
ちなみに目を閉じて泳ぐと100%曲がってコースロープか人に激突します(笑)スイマーの方は泳ぎながら動的瞑想をしたい?でしょうが目は開けておいてくださいね。
赤ちゃんにとっては偉大な一歩だ
2020/09/06
昨日長女(11ヶ月)が立っていました。最近立てるようになったのですが、少しグラグラと揺れながらもこちらを見て不敵な笑みを浮かべています。二本しかない下の歯を上唇にひっかけ猪木さながらにアゴを前に突き出しています。
なんだか自信に満ち溢れています。まだ歩けたことはないのですが、前に足を踏み出そうとしているのです。
そして、、
一歩前に足を進める。転びそうになりながらも踏みとどまりバランスをとる。そしてもう一歩前へ。安定しています。その後三歩目、四歩目と歩いて行き、お尻を床へ。
満足そうな顔で座り込みました。
いつの間にこんな力がついていたのか...?おそらく日々のつかまり立ちなどの積み重ねで筋力やバランス感覚を養っていたのでしょう。そしてそれが昨日形となって現われました。
話変わって今朝のオンラインアームバランスクラスでも同じような成長を見られました。今日はいつも参加してくれているメンバーだったのですが、みんなちょっと前とは比較にならないくらい動けています。いつの間にそんなに力をつけたのか?という感じ。積み重ねの練習で徐々に力をつけ、ある時に一気に外からも成長がわかるくらいになるものですね。
気づいたらいつの間にか、というのがポイント。
いつかS君も言っていました。
「アーサナはできるようになるものではない。気づいたらできているものなのだ。」
なんだか「〜ではない。〜だ。」という言いまわしに当てはめてしまうとなんでも名言ぽく聞こえてしまうものですね。
赤ちゃんは歩けるようになるものではない。
気づいたら歩いているものなのだ。
Koki Aijima
「大」
2020/09/05
子どもの言葉はおもしろいですね。
次男(2歳)がこの前こんなことを言っていました。
「にんじんなんておおきらい!」
そう、「大嫌い」のことを「おおきらい」と言っていたのです。子どもってなかなかすごいですよね。
何がすごいかというと、息子の周りには「おおきらい」と言う人もいないし、ましてやまだ字も読めないのです。なのでいつか本田圭佑選手が「清々しい」を「きよきよしい」と発言したのとはまた違った回路です。彼は「嫌い」の強調として「おおきらい」という言葉を自ら作り出したのです。あるいは「だいきらい」という言葉をどこかで聞いて知っていて自分の中で「おおきらい」に言い換えたのです。
人間の脳って応用力がありますよね。
「大当たり(おおあたり)」とか「大食い(おおぐい)」といった言葉の強調の「大」を他の言葉にも当てはめられるのです。
そして今「おおきらい」と言っている次男もこの先周囲が「だいきらい」と言っているのを聞いて「おおきらい」とは言わなくなっていくのでしょう。
でもそもそも「嫌い」が訓読みである以上、その前に付く「大」も訓読みの「おお」と読むのが日本語の一般的な規則なのでしょう。「大雨(おおあめ)」とか「大食い(おおぐい)」とか。逆に後ろが音読みだったら「大洪水(だいこうずい)」「大食漢(たいしょくかん)」と言ったように「大」も音読みになる傾向が強いのです。
なので次男は単純に一般的な法則を当てはめただけで規則的には大正解(だいせいかい)だったのです。言語学ではこういう誤用を過剰一般化なんて呼んだりします。例えば英語でも"go"の過去形を"goed"と言ったりと一般的な変化を不規則変化の動詞にも当てはめてしまうのです。
でもこの一般化が出来るから人間は言葉をスムーズに使いこなせるんですよね。動詞毎に過去形を覚えていたら大変な作業です。。
子どもの発言からはこの一般化の誤用がよく観察できるので小さなお子様がいる方はぜひ観察してみてください^ ^
そうそう、アーサナをとる際の身体の使い方もそれぞれに共通する一般的な法則があり、その中にたまに例外があります。共通項を探しだすのは楽しいですよ。シンプルなアーサナを要素の多いアーサナに応用できたり。
こちらもヨガをしながらぜひ観察してみてくださいね!
東大生活物語 第一話「おじさん大学生」
2020/09/04
こんにちは。今日も暑くなりました。9月に入ってから涼しくなったり暑くなったり忙しいですね。うちの次男(2歳)は涼しい日には外を駆け回っているのですが、今日みたいな暑い日は一歩も歩かず「抱っこ抱っこ」モードです。自分に正直に生きていますね。
さて、先週で長く続いた東大受験物語が終わり、今週からは新たに東大生活物語が始まります。現役高校生の10コ上の28歳で初の大学に進学した男から見た東大とはどんなものなのか...?毎週少しずつ紹介していきます。それが終わったら東大休学物語にでもなるのか?という疑問はさておき本編に入りましょう。
前回の話↓
長いようで短い受験生活が無事合格という形で終わり、安心したのも束の間、今度は入学準備をしなければなりません。不備があっては大変と苦手な堅苦しい書類もちゃんと読み書類での手続きをこなしていきます。そして3月の後半には駒場のキャンパスで健康診断や入学相談会みたいなものに行われました。
相談会では現役の東大生(つまり年下の先輩方)が大学生活の疑問に答えてくれたりします。高校にもまともに行ってない僕からしたら単位制というのも初めてで、いまいちよくわかっていません。仕事と大学を両立させるためには授業スケジュールの組み方が鍵になるので、わからない所はしっかりと質問しました。
そこで面白かったのは、年齢問題。質問を答えてくれるのはだいたい20歳前後の若い子達なのに話を聞いているとしっかり先輩に見えるのです。どこの世界でもそうですよね。その世界で経験のある人は大きく見える。年齢は関係ありません。先輩です。そして話し方が論理的です。
もう一つ面白かったのは、その先輩方から僕が全く年上に見られていなかったということ。これは「若く見られた」と喜ぶべきなのか、「未熟に見られた」と嘆くべきなのか。まあ見た目の年齢判断は難しいですからね。僕も全然他人の年齢はわかりません。そこに「新入生はだいたい現役高校生か、もしくは1~2年浪人した人だろう」という先入観が入るとさらに見極めが難しくなります。
よく見ると肌の質感が全然違うんですけどね。18歳の肌は輝きを放っています(笑)。
さて、その説明会で学んだことは「最初の学期に調子に乗って授業を詰め込み過ぎると後で痛い目見るよ。」ということでした。入学直後はいわゆる「4月病」といって予定を詰め込む人が多い。ただ5月あたりになって浮かれ気分が冷め始めた頃に、自分のキャパをオーバーしたスケジュールに気づき鬱になる、といった具合だそう。
(なるほどな、周りの雰囲気に流されないように自分のペースを守らなければ仕事も大学もダメになるな。。気をつけよう。)
なぜ気をつけなければならないかというと東大独自の進学振り分け(通称「進振り」)というシステムがあるからなのです。入学する時には全員教養学部所属、駒場キャンパスで2年生まで過ごします。その後、2年の中頃の「進振り」でそれぞれ進学する学部を決めます。(法学部、経済学部、文学部など。)
そしてその進振りには成績が必要なのです。セメスター(学期)毎にそれぞれの科目で成績(100点満点)が発表され、その平均点によって自分の希望の学部に進学できるかどうかが決まってきます。高ければ高いほど選択の幅が広がるのです。
つまり調子に乗って1年生の最初の学期に授業を取り過ぎるとテスト勉強やレポート作成が追いつかず2年の進振りに響いてしまうというのです。
(なるほどな、進振りか。覚えておこう。)
(「4月病」というワードも覚えておこう。)
(自分が案外若く見えるというのも覚えておこう。この先使えるかもしれない。)
そんな学びをして、その説明会を後にしました。
さて、3月末から4月頭までの慌ただしいイベントの数々。その数日後には学部ガイダンス、そして自分が所属するクラスの顔合わせが控えていました。多少は若く見られるおじさん大学生は10代の若さの波に乗って行けるのでしょうか...?!
To Be Continued...(毎週金曜日連載)
ゆるい体操??
2020/09/03
こんにちは。みなさんはヨガに対してどんなイメージを持っていますか?もしくは、ヨガを始める前はどんなイメージを持っていましたか?
少し前にお笑いコンビアンジャッシュの児嶋さんが載っているヨガの本が発売されたようです。まだ僕は中身を見ていないのですが、本のタイトルは「おっさんずヨガ」。男性をターゲットにしたヨガの本ですね。
親しみやすいイメージのある児嶋さんを起用した男性向けの本が出るのは僕も嬉しいのですが、よくよく考えてみるとそういった本を出さなければならないほど男性のヨガ人口は少ないのかもしれません。(ヨガ業界からしたら逆に狙い目ということ。)
僕自身は男女は関係ないなと思ってるのですが、実際問題ヨガに抵抗のある男性も多いのでしょう。僕が参加したインストラクター養成講座も男性は僕一人でした(笑)
先日ヨガパーソナルを受けてくれている男性の方とヨガのイメージについて話したのですが、ヨガをやったことのない方からすると「ゆるい体操」や「リラクゼーション」といったイメージが強いかもしれないとのことでした。
なのでやはりジムでの筋トレなどの方がわかりやすく人気があったりするのです。
でも実際ヨガをやってみると相当筋トレ要素が強いんです^^; 自分の体重を支えるポーズが多く強度は思った以上に高いのです。筋肉量はかなり増えます。なおかつ全身を隅々まで使うので身体の使い方がうまくなります。(そして何よりそれに付随した精神面の大きな変化があります。)
特にアナ骨はヨガの中でもトップクラスにキツい部類に入りますがその分効果はピカイチです。数えきれないくらいの変化がありますのでまずは実際にお試しください!
まあまずは児嶋さんの本がバカ売れして男性のヨガ人口が増えてくれることを願っています。(どんな内容なんだろう??ゆるい体操じゃないといいです笑)
脱力系男子
2020/09/02
僕の娘はもうすぐ1歳になりますが、彼女を見てると身体の使い方の大事なところがなんとなくわかってきます。赤ちゃんって声の出し方もうまいし顔の表情も柔らかく豊か。何がうまくできているかというと、
やっぱり「脱力」ではないかと思います。
いつかのブログでも書きましたが、全身の余計な力が抜けるとコア(特に背骨や下丹田)や足裏の意識が強くなります。結果的に無駄なく気持ちよく動けるようになる。その状態でアーサナをとれば更に身体が整います。
脱力といっても全身の力を全て完全に抜くわけではありません。重力に対して力が入り過ぎているところを解除する感覚です。
僕がやっている脱力のコツとしては、
1.深い呼吸
2.肩をストンと落とす
3.意識を自分の外側に広げる
3は自分を包むオーラのようなものをイメージして自分の周りに想像できるだけ大きく広げていきます。(球型でも人型でもかまいません。)
脱力がうまくできると精神も落ち着き堂々とした心構えになります。体内の流れも良くなる感覚があると思います。
上のポイントがわかりづらい方には気功の甩手(せいしゅ)がオススメ。スワイショウとも呼ばれています。
やり方は簡単。立った状態で両腕を同時に前後に振るだけ。前に降った時には手が肩の高さくらいまで上がります。振り子が揺れるように力を抜いてただブラブラします。細かいポイントはあるのですが、最初は何も気にせずただブラブラするだけでいいと思います。
3分くらい振り続けていると手がだんだんとポカポカしてきます。肩周りから全身の脱力も出来上がります。本当にオススメ。
ただたくさんやっていると歩く時の手の振り方も左右同時になっちゃいます(笑)
ショーシャンク豪雨
2020/08/31
今朝も幼稚園に自転車で長男を送って行ったのですが、帰り道に大雨に降られました。ゲリラ豪雨。久々に全身びしょ濡れになりました。自転車の前に乗っていた次男もびしょ濡れ。
もうどうせ濡れているならと家の前でしばしの間次男と2人で雨のシャワーを浴び続けました。そして今回の写真。
映画「ショーシャンクの空に」。
僕が今までに観た中で一二を争うくらいの映画です。(映画通でもなんでもないですが…)内容は書かない方がいいと思うので書きませんが、見終わった後に爽やかなエネルギーが湧いてくるような映画です。(だいぶ前に観たので細かい内容は忘れてしまったけど。)
オススメです。
考えてみれば人生も映画のようなものですね。浮き沈みもありドラマがある。2時間にまとめられた映画のように凝縮された場面ばかりではないけどそれぞれにストーリーがあります。
でも毎日が単調だと感じる方もいるかもしれません。そんな時は自分がワクワクすることを見つけられると楽しくなります。新しいことを見つけてもいいし自分の毎日やっているものの見方をちょっと変えるだけでもいいと思います。
好きな映画の主人公のような気持ちで過ごしてみませんか?
たまには雨浴びるのも楽しいですよ^ ^(一人でやっていたらちょっとヤバいかもしれませんが。)
ビルじいさんと武蔵
2020/08/30
今日何気なくオンラインニュース記事に目を通していたらこんなタイトルが目に飛び込んできました。
——大往生のハシビロコウ 「ビルじいさん」雌だった 伊豆シャボテン動物公園——
この一文の中にけっこうな要素が入っちゃってますが記事の内容としては以下のような感じです。
伊豆シャボテン公園で「ビルじいさん」と呼ばれ親しまれていたハシビロコウが老衰で死んだ。その時の年齢がおそらく世界最高齢、大往生だった。しかし解剖の結果「ビルじいさん」は雌だったことが判明した。
記事によるとハシビロコウは雌雄の見分けが難しいようです。けっこう見分けが難しい動物は多いんですよね。
この記事を読んであることを思い出しました。それは僕が小学生の頃から10年近く家で飼っていたフクロモモンガのこと。武蔵(むさし)と百惠(ももえ:なぜか「惠」は旧字)という名前のついた仲良しペアでした。
フクロモモンガはその名の通りカンガルーと同じ有袋類で子育てをお腹の袋の中で行うのですが、何年経っても武蔵と百惠には赤ちゃんが生まれなかったのです。仲はすごくよさそうなのに。
そして8〜9年経ち2匹とも老衰で死んでしまいましたが、最後まで赤ちゃんが誕生することはありませんでした。そしてそのすぐ後くらいに僕はあることを知りました。
フクロモモンガのオスは頭のてっぺんがハゲるそう。
そして武蔵はといえば、、
ハゲてなかった(笑)
メス2匹のペアでした(笑)昔はインターネットも普及してなかったので雌雄の見分け方も簡単にはわからなかったのです。
(武蔵、女の子だったのか。うすうす気付いてはいたけど…)
(大剣豪みたいな名前つけちゃってごめんなさい。)
少し武蔵には悪い気がしましたが、「武蔵」って女の子の名前でもありそうですね。昔ポケモンのアニメに出てきた悪役の女の子の名前も武蔵だったような。。
いずれにしても一緒に過ごした思い出は変わりません。「ビルじいさん」が今更「リズばあさん」になるわけでも「武蔵」が「お通」になるわけでもありません。2人(1羽と1匹?)ともありのままの自分を生きたのです。
ありがとう武蔵、ありがとうビルじいさん。(ビルじいさんとは面識がないけれど。。)
人間の世も一昔前よりはだんだんと性の自由度が高まり、ありのままの自分を生きられる人が増えてきているように思います。
ちなみにハシビロコウは普段はじっとしていて動く時もゆっくり動くのでヨガに向いているんじゃないかなと思います。
次回「フクロモモンガ、レジ袋有料化に物申す!の巻」(笑)
関連エントリー
-
 内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
-
 二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
-
 春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
-
 iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
-
 役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以
役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以











