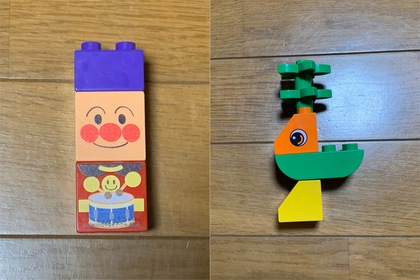- ホーム
- RSYブログ
RSYブログ
郷愁
2020/02/22
今日は朝のアナ骨が終わった後水泳の仕事で秋葉原まで行ってきました。なかなか普段行くことのない場所です。
秋葉原には何年か前に海外の友達の観光案内で行ったきりだった気がします。今日街を歩いてみてその時の思い出が蘇ってきました。特にあの場所に行った時の思い出。。
そう、、
メイドカフェ。
なかなか自分だけでは入る勇気の持てない場所。ヨガスタジオのさらに上の上を行く異空間。勇気を出して海外の友達を連れて行きました。カフェに入るなり初めてなのに「お帰りなさいませ、ご主人様。」とメイドさんが出迎えてくれました。そこは新世界でした。
入った後に気づいたのですが、観光に連れてきた友達は日本語を話せないのでメイドさんとの会話はほとんど全部僕がしなくてはならない状況でした。なので友達の頼みたい「ぴよぴよひよこライス」や「あちゅあちゅラテ」なんかも全部僕が頼むことになりました。当時はまだヨガも始めていなかったのでさすがに呼吸が乱れ、心臓の鼓動も速くなっていました。
一番ハードルが高かったのは、オムライス(ひよこライス)にメイドさんがケチャップでお絵描きをしてくれる時に一緒に手でハートを作りながら「もえもえキュン!」と言って愛情を注がなければならなかったこと。その時、人の顔が本当に熱く赤くなることを知りました。初めての経験でした。
ただ最初は恥ずかしかったカフェも後半になると不思議と楽しい気分になってきました。人間には適応能力があるのです。そして帰りの際にはメイドさんに「いってらっしゃいませ、ご主人様。」と声をかけてもらいました。そうか、ここが帰る家なのか。。
「いってきます。」
春の訪れを告げるような風が吹き抜ける午後の秋葉原。やわらかな陽光が心の奥をくすぐります。僕は未だ帰る約束の果たせない故郷(いえ)に想いを馳せながら仕事に向かいました。
色々
2020/02/21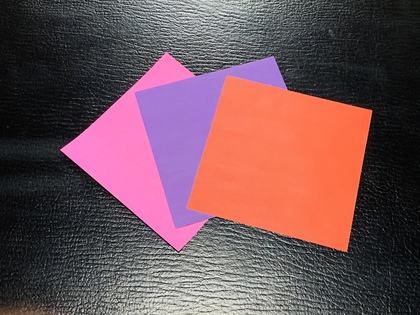
同じものに対する色の見え方、感じ方は人それぞれなようです。今日も妻と色に関しての意見が分かれました。
僕が「紫」だと言った服を妻は「青だ」と言います。人によってここからは紫、ここからは青、など境界線が違うようです。
そしてもっと面白いのは同じものでも人によって本当に見え方が違うこともあるということ。何年か前に流行った「ドレスが何色に見えるか?」問題。これも家族の中で意見が割れました。同じドレスを見ているのに全く色が違って見えるのだから不思議です。今日息子たち2人に初めてこの画像を見せてみたら僕と同じ色に見えていてなんだか安心しました。興味のある方はドレス画像の載っている記事へのリンクを貼りますのでぜひチェックしてみてください。家族の方がいたら比べてみるのも面白いかも。↓
他人と同じものを見ていると思っていても全然違ったなんてことは多々あるのかもしれませんね。まさに色々です。
ちなみに僕のブログ、妻は全く見ていません。
アーサナメモvol.34
バーラアーサナ(チャイルドポーズ)
2020/02/20

昨日写真に写っていたS君は最近よく生麹をくれます。この生麹で甘酒を作ってみると乾燥麹とは全然発酵の速度が違うのです。すぐに甘酒ができてしまう。味もなかなかまろやかです。発酵のはやい生麹、保存がきく乾燥麹、それぞれの長所がありますね。
まあ麹の話は置いておいて今日もアーサナ紹介です。ヨガクラスで休憩の姿勢としてよく行われるバーラアーサナです。チャイルドポーズという名前の方が馴染みがあるかもしれません。昨日、一昨日と紹介した背中を強く使うアーサナの後にはそれを中和するものとして特に役立ちます。またちょっとした意識の持ち方次第で休憩以上の効果があると思います。
メモ
・上半身が脱力できるように手や頭の位置をセットする。手は前に伸ばしたり、額の下に両手を重ねて置いたり、お尻の横に置いたりと自分の体型や感覚に合わせて調整。顔は床に向けていても横を向いてもOK。
・脱力した肩や腕の重みで背中を伸ばす。
・腿の上にお腹が当たって苦しければ膝を開いて隙間にお腹を落とす。
・膝が曲がりきらずお尻が浮いてしまう場合はかかととお尻の間にブランケットなどをはさむ。
・腿にお腹や肋骨が当たると自分の呼吸の動きに集中できる。
・脱力が当たり前にできるようになってきたら、吐く息で仙骨から頭頂まで背骨に沿って気(エネルギー)が流れ、吸う息で頭頂から仙骨まで気が戻るのをイメージする。
イメージの力を借りると単なる休憩に留まらず自分の力を上げる効果や瞑想効果もあるアーサナです。眠る前の布団の上などでも行えます。アームバランスなどで動くことができるようになってきたらこういった静のアーサナにも挑戦していくといいかもしれませんね。
アーサナメモvol.33-2
アルダ・プールヴォッターナアーサナ
2020/02/19

今日の朝のクラスでは何人か鼻をグズグズさせている人がいたので聞いてみると、やはり花粉症でした。今日のような天気は花粉が大量に飛んでいるようです。先日ブログに載せた鼻うがいは花粉を洗い流すのにも良いのでぜひお試しください。
今日のブログは昨日のプールヴォッターナアーサナの補足です。昨日紹介したような膝を伸ばすやり方だと負荷が高過ぎることがあるので、もう少しやりやすいバリエーションを写真に載せました。アルダ・プールヴォッターナアーサナ、いわゆるテーブルポーズです。
昨日のアーサナと異なるのは膝を曲げてスネを床に対して垂直に保つ点。膝を伸ばすよりもお尻を高く保ちやすくなります。このアーサナに慣れてきた方は写真のように片足を浮かせたり、対角線の片足と片手を離したり変化をつけても面白いと思います。写真の左上から右下に行くにつれて難易度は上がります。
なかなかコアの力が試されるアーサナ、どこまでできるでしょうか?
たまには気分を変えて今日の写真はS君実演です。
アーサナメモvol.33
プールヴォッターナアーサナ
2020/02/18

この冬はけっこう気温の上下動が激しいですね。みなさん体調は大丈夫でしょうか?
メモ
・足裏は地面につけるように足首をまっすぐ伸ばす。
・お尻の位置はできるだけ上げて体で少しアーチを描くように。
・肩甲骨を背骨の方に寄せて胸を開く。
・頭は呼吸がしやすい位置にセットする。(呼吸ができるのであれば首を反って頭をだらんと垂らす。
背中やお尻などの背面の力がないと足裏が床につかないかもしれません。その場合は膝を90°に曲げて足裏を床につけるテーブルポーズから始めます。呼吸も浅くなりがちなので意識的に行いましょう。
背中の力を使うと気分がすっきりしたり明るくなったりします。お腹を使うプランクとの感覚の違いも確かめてみましょう。
守り過ぎの罠
2020/02/17
最近気づいたこと。
防水の靴は軽い雨なんかは完全に防いでくれる。でも土砂降りの雨で水が靴紐の辺りから中に侵入した場合、なかなか乾いてくれない。防水仕様で湿気が外に出て行ってくれないから。
人間の心身もそれに似ていて、守ろうとし過ぎると、弱る。
鼻うがい×専用容器
2020/02/16
昨日の午後は頭痛と腹痛がありなんだか調子が優れませんでした。夜になっても治らず気分も良くなかったのですが落ち込んでばかりいられないと思い、気合いを入れるために妻に、
「俺の辞書に"落ち込む"という文字はない!!」
と両手を上げながら叫んで宣言すると、
「何言ってんの?落ち込んでばかりの人生じゃん。」
と一蹴され撃沈しました。おかげで今日は元気です。
さて、一昨日のアナ骨クラスの最初に菌やウイルスなどの話題が出たので、「鼻うがいはなかなか効きますよ」という話をしました。すると参加者の一人が、
「鼻うがいは知り合いに勧められて一度やったことがあるけど鼻がツーンと痛くてそれ以来やってないの。」
とのこと。話を聞いてみるとただのぬるま湯でやってしまったようです。それじゃ痛いわけですね。プールで鼻に水が入るようなもの。鼻うがいで使う水には塩を入れないと浸透圧の関係で粘膜に刺激を与えてしまうのです。
鼻うがいを快適に行うには0.9%前後の濃度の食塩水を用意します。1リットルの水に対し約9gの食塩を入れます。冷たい水よりもぬるま湯を使うとなお刺激が少ないです。
そして用意した食塩水をコップいっぱいに満たして片鼻で吸い上げ口から出せば良いのですが、この方法は慣れが必要で初心者には少し難しいのです。そこでもう少し簡単な方法があります。
まず「ハナノア」という鼻うがいの為の洗浄液製品を買います。(←買ってる時点で「簡単」ではない気がしますが。。確か700〜800円くらいだったかな。)ハナノアには写真に載せたような鼻うがい用の容器がついています。これがなかなか優秀です。この容器に先程の食塩水を入れて片鼻に噴射するだけで、液体が鼻の奥に届き逆の鼻から出てきます。ただ容器を手で押すだけなので簡単です。
もちろん食塩水ではなくてハナノアの洗浄液でもかまわないと思います。僕は余計なものが入ってない方が感触が良いので食塩水です。
風邪予防や花粉症軽減にもなるのでオススメです。お試しあれ。
とはいえ心
2020/02/14
昨日は「身体に合わないものを除いていけば調子は上がりますよ。」みないなことを書きました。当たり前の話ではあるのですが、この話にも注意しなければならない点があります。
身体だけの問題を考えれば合わないものを除けば確かに調子が上がります。しかしそこにこだわり過ぎてしまうとかえって逆効果になることもあるのです。
「これは身体に悪そうだからやめておこう」とか「身体に良いものを食べなきゃ」などと考え過ぎてしまうと精神面があまり良くない状態になり身体の調子も下がってしまいます。例えば、何の躊躇もせず「マックにいこう」という人はけっこう元気な人が多いですよね。毎日青汁を飲んでいる人よりも元気なことがあります。身体が元気だと健康に対する不安がなく本能の赴くまま行動ができるのです。
ヨガクラスなどでは普段身体→心というアプローチを表立って行っていますが、心→身体というアプローチはとても重要です。「些細なことは気にしない」とか「今を楽しむ」とかそういったことです。心が変わることで身体もいつの間にか変わっています。
とはいえ明日から毎日マックに通いなさい、という訳ではありません。昨日のブログでは身体→心のアプローチ、今日は心→身体のアプローチに触れました。極端になり過ぎないバランス感覚が大事だと思います。
そしてバランス感覚よりももっと大事なのは「気」を大きく持つことだと思います。
身体に良いもの、悪いもの
2020/02/13
身体に良いものや悪いものは人によってもだいぶ違うし状況にも左右されます。
お医者さんが「この食べ物には体に良い成分がたくさん入ってるからぜひ食べなさい」と言っていても、人によってはそれを食べると調子が落ちることがあります。当たり前ですが体質はみんな同じではないのです。
また状況も大事です。極端な話、山で遭難して5日間水以外何も口にしていないような極限状況でもし目の前にコストコのショートケーキが現れれば(どんな状況?)、それは命を救う奇跡の食べ物になるでしょう。(極端過ぎる…)
まあこんな極端な話でなくても個人の体質やその時の身体の状態によるので、絶対的に良いもの悪いものというのはないんですよね。(多くの人や状況に当てはまる良いものや悪いものというのはあると思います。)だから成分などだけでは判断ができないのです。
じゃあどうしたら判断できるのか?簡単です。頭ではなく身体で判断します。健康に良いものをたくさん摂ろうとするのではなく、自分に合っていないものを排除したほうが調子が上がると思います。
自分に合わないものの判断基準の例をあげると、
・食べた後にやる気が落ちる。
・食べた後気分が落ち込む、イライラする。
・食べた後いつまでもお腹に残っている気がする。
・食べた後眠くなる。
・食べた後集中力が下がる。
・食べた後呼吸がしづらくなる。
・明らかに依存性の強いもの。
などです。上記のような物を生活から除くとやる気が出てきてストレスにも負けなくなってきます。
私は物を食べて調子が下がることはないよ、と思っている方も調子を下げているのに気づいていないだけのこともあります。慢性的に調子を低い水準で保っているパターン。その場合は、何かを絶って調子が上がることで初めて今まで調子が落ちていたことに気づきます。
まあ何を体に入れても元気いっぱい常に絶好調の人もいます。羨ましいですね。
自分を観察してみると面白いですよ。
ところで今日の写真は内容にはなんの関係もない最近気に入っているアーサナです。
関連エントリー
-
 内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
-
 二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
-
 春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
-
 iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
-
 役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以
役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以