- ホーム
- RSYブログ
RSYブログ
タイムリミット
2019/06/27
今日のタイトル「タイムリミット」は昨日話に出した制限時間を言い換えただけです。気分を変えたかったので。少し言葉の印象は変わりますが、同じ意味として使っていきますね。
だいたいの物事においてタイムリミットはあると思います。そして昨日書いたようにタイムリミットがあることが、やる気に火をつけたり集中力を上げたりします。
誰にでも共通の普遍的なタイムリミットは「人生の終わり」だと思います。一生のうちにやりたいことはそのタイムリミットまでにやらなければならない。ただ誰もが意識するこの人生のタイムリミットですが、若干具体性に欠けます。だいたいの人は「明日地震で死ぬかもしれないから今日できることを全身全霊やってやる」とはならないと思います。そんなことができるのはごく一部の人、生命力が飛び抜けて高くエネルギッシュで「今この瞬間」に集中しきれる人だけです。そんな人はもはやタイムリミットなんて概念はなくても大丈夫ですね。
それ以外の人はやはりペース配分のことを多少なり考えて生きていかなければなりません。ただタイムリミットはやはり必要です。人生の終わりよりももっと細かく区切ったタイムリミットです。昨日の電車の中の時間もその一つですね。
世の中には強制的なタイムリミットも多いように思います。学校の宿題や仕事の締め切り、幼稚園の迎えなど。あまりに作業量とリミットのバランスが崩れている場合は心身を壊す原因にもなりますが、多かれ少なかれ誰でもタイムリミットの中で生活しています。
では生活に縛られた強制的なものは置いておくとして、みなさんが本当にやりたいと思っていることに関してはどうでしょうか?やりたいこととは自分の中の大きな夢でも日常の些細なことでもかまいません。
タイムリミットをうまく捉えて自分に生かせているでしょうか?
生き急ぐのとは違います。もちろん自分の心身の状態に合わせて緩急をつけたペース配分は必要です。
僕も限られた時間をどう使うかは今も試行錯誤ですが、もしみなさんの中に「やりたいことがうまく行かない」「なんだか人生が滞っている感じがする」などの悩みを持つ方がいましたらもう一度時間の使い方について考えてみてください。もしかしたら何か変わるかもしれません。
制限時間
2019/06/26
今日は過ごしやすい天気でしたね。でも明日からはしばらく雨だそうです。傘を持って出かけるのはどうも気が重いです。特に電車に乗る場合には。そして今日も電車の話です。
電車の中では集中できるという昨日の話を書いていて思い出したのは、大学で同じクラスのG君の話。
G君はとてもエネルギッシュで明るい大学の同級生(9歳年下ですが...)です。僕の結婚式でも歌を歌ってくれました。彼は高校卒業後一度早稲田大学に入学したのですが、なんだか思い直して東京大学に入りたくなったそうです。どういう事情かは詳しく聞いていませんが、早稲田大学一年の時に親には内緒で東大受験のための勉強を始めたそうです。
親に内緒だから家で勉強ができない。彼が勉強場所に選んだ場所は山手線の電車の中だったのです。山手線はグルグル回っているどこか遠くへ行ってしまう心配はない。彼は山手線に揺られながらひたすら勉強をしたそうです。そして無事合格。合格してから親に報告もできたようです。
すごい集中力ですね。東大に合格できるかどうかは別として、やはり電車内で集中できる人はけっこういるのではないでしょうか。
そして昨日は書き忘れましたが、電車で集中しやすい要因として制限時間があげられると思います。目的地に着くまでの時間には限りがあり、その時間を目途に今していることを区切りの良い所まで終わらせようとします。本を読んでいるなら今読んでいる章まで読む、課題をやっているならこの問題まで解く、今日のブログは目的地までに書き上げる、、など。時間が有り余っている時よりも密度の濃い作業が可能になります。(上のG君は山手線グルグルなので果たして制限時間という概念があったのかはわかりませんが。。)
この制限時間は電車に乗っている以外の場面でも多々大事になってくる概念だと思います。
では寝る時間なのでここら辺でタイムオーバー、続きは明日書きます。
おやすみなさい。
集中しやすい場所
2019/06/25
みなさんは日常的に電車を利用していますか?普段車が多い方、歩きや自転車の方、生活スタイルによって交通手段は様々だと思いますが、僕は毎日のように電車を利用しています。
行き先はたいてい渋谷や目黒、新宿あたりになりますので、最寄りの京王よみうりランド駅からだと乗り換え含めて片道40分前後になります。すると往復で1時間20分、細かい移動もありますので、一日約1時間30分くらいは電車に揺られている生活です。一日24時間、起きている時間が僕の場合はだいたい17時間くらいですから、その中の電車の1.5時間というのはけっこうなウェイトです。
しかしながらこの電車の中の時間がなかなか有効なのです。僕にとって電車の中は集中力の発揮できる場所なのです。
本を読むにもブログを書くにも何かアイデアを浮かばせたい時にも集中できます。読みたい本はいつも電車で読みますし、このブログを書いているのも渋谷に向かう電車の中です。(ブログはたいてい電車で更新しています。)
なぜ電車の中で集中できるかは何点かのポイントがあると思いますが、
1. 家の中のように集中力を妨げるものがない。
2. その物事しかやることがない。
3. 図書館と違い雑音や揺れがある。
などでしょうか。
3に書いた電車の揺れは座っていたりすると逆に眠気を誘うものになりますが、揺れに対抗して体幹や脚を安定させようとする動きは全身の血流を良くして集中力を高めるように思います。また電車や周りの人の雑音があることで、脳はかえって集中しようというモードに入るのだと思われます。僕は静かな図書館ではいつも眠りに落ちてしまいます。もちろん図書館の方が集中できる方もいますので個人差は大きいですね。
まあそもそも超満員の電車で読書などできないなど利用時間帯によっても制限はかかってくると思います。ありがたいことに僕は朝早く電車に乗ることがあまりないので快適に本などを読めます。ですので電車に乗っている毎日の1.5〜2時間はかなり充実した時間になっています。
みなさんは特に集中できる場所というのはありますか?その場所での身体や脳の状態がいつでも集中力を上げられるようになるヒントになるかもしれません。環境と身体の関係について少し意識してみるのも面白いかもしれませんね。
極楽鳥
2019/06/24
昨日の夜はHIP JOY YOGAのレッスンでした。
このクラスでは通常基本的なアーサナの組み合わせでお尻を刺激し股関節周りの機能性を上げていくのですが、先週と昨日はレッスンの最後に少し難しめのアーサナを行ってみました。
そのアーサナは"スヴァルガ ドゥヴィジャアーサナ”「極楽鳥のポーズ」。
なぜ難しめなのかというと、抑えるべき要素の数が少し多いから。股関節周りの筋力と柔軟性、肩周りの筋力と柔軟性、バランス感覚(特に足裏とお尻で調整する力)などが必要になってきます。
最近はHIP JOY YOGAに参加いただいている方の股関節の動きが良くなってきたので、もしかしたらと思い試しにやってみたらけっこう良い感じでできていました。背中の後ろで腕をつかむことも慣れていなかったはずなのですが、今まで繰り返し行ってきた他のアーサナの影響で肩周り(肩甲上腕関節、胸鎖関節)の動きが良くなって手が届くようになっています。軸足で支えるバランスも良くなっていて多少ぐらつくものの片足で立てていた方が多かったように思います。
身体の中で特に大切な股関節と肩関節を使うこのアーサナ、あと何週かは練習していこうと思います。自分の成長を感じてみてください。
ちなみに極楽鳥はニューギニア辺りに生息するフウチョウの仲間のこと。鮮やかな体色や変わった形の羽根、ユニークな求愛のダンスで知られます。そんな極楽鳥のようなアーサナをとれるようになりたいものですね。(僕はまだ脚が伸びきりません...写真はウォーミングアップなしで撮ったので上半身もねじれてしまっています^^;)
羽化
2019/06/23
昨日までの筋肉の話からは一転、今日はまた家で飼っているカブトムシの話です。
昨日は蛹になっていたカブトムシの中で一番小さいものが羽化しました。僕は仕事で一日外に出ていたので羽化の瞬間は見られなかった(見れなかった)のですが、妻が羽化直後の白い羽のカブトムシの写真を撮っておいてくれました。まだ体も柔らかい状態です。あまり動かずじっと休んでいたみたいです。
蛹化の時も幼虫からの変化に驚かされましたが、今回も豪快に蛹の皮が脱ぎ捨ててありました。全くの別人(別虫?)のようです。
そういえば人間にも「一皮むける」なんて言葉を使ったりしますね。何か大きな試練などを乗り越えた時に別人のように成長することがあります。そんな特別だと思える出来事でなくても明らかな変化が起きることもあります。新たな出会いだったり別れだったり、日々のトレーニングの中にもそんな瞬間が潜んでいます。
カブトムシのような完全変態の生き物のように姿形がそっくり変わるわけではありませんが、人も内面や持っている雰囲気はやり方次第でどんどん磨かれていくのではないでしょうか。もちろんそこには身体面の問題が深く絡んでいます。
ところでカブトムシは体の小さい個体から羽化していくようです。大きい個体には力では勝てないのでスピードで勝負する。生き抜くための知恵ですね。
小さな虫にも生きるヒントを見出せる気がします。
遅筋と毛細血管
2019/06/22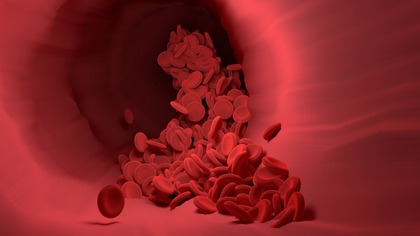
冷えと筋肉の関係の続きです。昨日は身体を温めるには筋肉が必要だけれどもその筋肉にも種類があるという話でした。おおまかに分けると筋肉は遅筋と速筋に分類できます。(本当は速筋はさらに2種類に分類されています。)
筋肉によって体内では熱が産生されますが、その熱を身体の隅々にまで届けるのは血液、血液が流れるのは血管です。
血液を運ぶ血管を増やすことは血行促進につながるのですが、遅筋の周りには毛細血管が多く速筋の周りには少ないのです。遅筋を鍛えることでその周りの毛細血管が増えてきます。
筋肉量が多い人でもジムで高重量のウェイトを扱っている筋肉隆々の人などは寒さに弱い場合があります。逆に一見細身で筋肉がなさそうでも遅筋がしっかり鍛えられている人の血行は良かったりするのです。(遅筋は鍛えても大して太くなりません。)
ヨガは基本的に呼吸を続けながらゆっくり動くので有酸素運動の要素が強くなります。ですので遅筋を鍛えやすい。ところどころで瞬間的な力が必要な箇所では速筋も使いますが、動き続けるための持久力が必要なので遅筋に近い特性を持った速筋が増えていくのだと思います。
遺伝的に速筋線維の割合が多い僕からすると、ヨガで行う持久力を伴うゆっくりした動きは「苦手」なものなのです。ですが苦手なゆっくりな動きは身体のバランスを整え体調も大幅に改善しました。その中には血行促進による冷えの改善も含まれます。今では長くアーサナをキープするのも心地よいくらいです。ヨガを始めた当時はじっとキープするのが辛くてしょうがなかったです。
特に特殊なスポーツや仕事に携わっているわけではない場合には、遅筋を鍛えることに注目した方が体調を維持、改善するには有効なのではないでしょうか。
冷え性などでお悩みの方は特に呼吸を止めずにじっくりゆっくり動くことをこころがけてヨガを行ってみてください。もちろん冷えにはホルモンや自律神経の働きなども絡んでくるとは思いますが、毛細血管が増えることはそれらの要素の改善にも繋がると思います。
ということでヒラメではなくマグロを目指しましょう。(ヒラメ的なスポーツや仕事をしている人はヒラメのままでいいと思います。)
遅筋と速筋
2019/06/21
昨日の続き、冷えに関してです。
寒さに強いか否かには複数の要因が絡んでいるとは思いますが、その中でも特に筋肉の影響はかなりあると思います。身体の筋肉量が多いか少ないかは冷えに関わります。さらには筋肉の種類が関わってきます。
今回のテーマはタイトルにあるように、
遅筋と速筋。
遅筋は瞬間的に大きな力は発揮できませんが、有酸素運動をする時に使われる持久力に特化した筋肉。周りに毛細血管も多く赤い筋肉(=赤筋)とも呼ばれます。(赤色は遅筋に多く含まれるミオグロビンというタンパク質の色)魚でも長時間遊泳する持久力型のマグロは赤身です。
速筋は短距離走などの無酸素運動の際に使われる筋肉。短い時間で大きな力を発揮する時に使われます。白い筋肉(=白筋)とも呼ばれます。魚では普段じっとしていて必要な時だけ素早く動くヒラメにはこのタイプの筋肉が多いです。白身魚ですね。
この間にピンク筋とも呼ばれる中間型の筋肉もあるのですが、ここではわかりやすく遅筋と速筋の2種類だけの話をします。
この遅筋と速筋は全ての人が身体の中にどちらも持っています。筋肉によっても遅筋が多いかか速筋が多いかの傾向は異なります。(例えば同じふくらはぎの筋肉でもヒラメ筋は遅筋の割合が多く、腓腹筋は速筋繊維が多いです。ただ上に述べた魚のヒラメは速筋中心ですのでヒラメ筋と混同しないようにしてくださいね。)
この遅筋と速筋の割合は人によって生まれつきの傾向が異なるのです。遺伝子によってそれは決まります。今の時代は便利で7000円程で検査キットを取り寄せて簡単に検査することができます。気になる方はネットで「スポーツ遺伝子」などと検索してみてください。
この検査では自分が、
速筋型
中間型
遅筋型
のどれに属するのかを調べることができます。それによって持久力系のものが向いてるのか瞬発力系のものが得意なのかなど自分の傾向を把握できたりします。まあでもこの遺伝子の他にも様々な要因が存在しますので、あくまで目安の傾向ですが。ほとんどの方が中間型ですしね。
ちなみに僕は速筋型です。
肝心の冷えと筋肉の種類の関係については長くなってしまうのでまた明日に持ち越します。
明日の朝のアナトミック骨盤ヨガでは遅筋(赤筋)を中心に鍛えていきます。
冷え
2019/06/20
今日は蒸していて暑いですね。歩くだけで汗をかきます。こんな日ですが「冷え」に関することを書きます。
先週の金曜日にとある都立高校の水泳部の指導に行ってきました。その水泳部の顧問の先生は昔僕が通っていた高校でも水泳部の顧問をしていた方でした。その先生からの頼みでここ3年ほど、たまに水泳部の練習を見に行っています。
高校生が水泳を頑張っている話はいずれ書くかもしれませんが、今日のテーマ別、「冷え」です。高校の外プールはこの時期とにかく寒いのです。
先週の金曜日は雨も降らず気温もそれなりに高かったのですが、それでも高校プールの水温は22℃くらい。普段プールに入らない方は、「なんだ、20℃以上あるならたいしたことないじゃん」と思うかもしれませんが、この水温は氷水に入っているような感覚です。普通の温水プールはだいたい31℃前後に水温を調整してありますので、それよりも10℃近く低いのです。
僕が水に入ったのは練習時間の最後の15分だけなのですが、体は縮こまって鳥肌が立ち、声が震えてきました。筋肉の動きも悪くなるので泳ぎも若干ぎこちなくなります。プールから上がった後もどっと疲れが出てしまいました。
ここで改めて思い出したのが自分は寒さに弱いということ。まあ22℃のプールなんて誰が入っても寒いのですが、周りの人の身体反応などを見てみると僕は明らかに寒さが苦手なようです。
これはなぜでしょう?人によって寒さに対する耐性が違うのは何が原因なのでしょうか?
色々と要因があるとは思いますが、あるポイントに絞って考えてみたいと思います。長くなってしまいそうなので続きはまた明日書いていこうと思います。
それではまた。
写真撮影
2019/06/19
今日は朝のRoot Yoga Moveが始まる前の10分くらいを使ってホームページに使うための写真撮影を行いました。何種類かのアーサナをとった状態での撮影でしたが、普段水曜日にはやることのないアナ骨のポーズがあったりして少しきつかったかもしれません。ご協力いただいた参加者の皆さまありがとうございました。
ところで今日は珍しい出来事がありました。写真撮影中、なにやらスタジオのドアがガチャガチャ鳴っています。なんだろう?とは思ったものの鳴り止んだのでそのまま放っておきました。でも少しするとまたガチャガチャ鳴るのです。そして次の瞬間にはノックのような音も聞こえました。
さすがにおかしいぞ?と思い撮影中でしたがドアのところへ駆け寄りました。するとそこで初めてスタジオのドアの鍵が内側から閉まっていることに気づきました。急いでドアを開けるとそこにはいつもの参加者Tさんが立っていました。
「鍵はしまっているし先生の自転車もないし今日はレッスンが休みかと思って焦りました。」とのこと。Tさんは何分かそこでガチャガチャしたりスタジオの小窓から中の様子をうかがっていたようです。少しの間放っておいてしまい申し訳なかったです。ちなみに僕の自転車が停まっていなかったのは昨晩クギを踏んでパンクし今日は歩いてスタジオに来ざるを得なかったからなのですが。。
そしてなぜスタジオの鍵が閉まっていたかと言うと、、
直前にスタジオに来たMさんがスタジオに入った途端、自分の家での習慣で鍵を閉めてしまっていたようです!
でも自分の家と勘違いするくらいスタジオに馴染んできたなら嬉しいことです。
こんなこともあるものですね。ではまた明日。
アナ骨@若葉台iプラザ
2019/06/18
タイトルにあるように7月11日から若葉台駅近くの稲城市立iプラザでアナトミック骨盤ヨガの出張クラスが始まります。
今のところ予定しているのは、
7月11日、18日、25日
8月8日、15日、22日、29日
9月12日、19日
全て木曜日の9:30〜11:00の90分クラスです。
場所はiプラザの大会議室で行います。
これからの希望次第で木曜日の朝以外にもクラス数は増えていくかもしれません。希望を聞きながら臨機応変に行っていこうと思います。若葉台付近にお住まいの方、ぜひご参加ください。心身が変わりますよ。
ところで昨日はその若葉台クラスの宣伝用に写真が必要だと思い、家族で稲城中央公園に写真(このHPのトップページ上部に表示される写真)を撮りに行ったのですが、やはり息子たちもヨガのアーサナを真似してとっていました。
その一枚が今回のブログの写真。見事なバカアーサナです。ヒザを腕に置いてないのでバカアーサナよりも難しいかもしれません笑
子どもはどんどん器用に色々なことを吸収しますね。スポンジみたいです。そしてヨガは子どもの発達にもすごく良いようです。この辺のこともそのうちブログで書いていこうと思います。
それでは良い一日をお過ごしください。
関連エントリー
-
 内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
-
 二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
-
 春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
-
 iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
-
 役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以
役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以










