RSYブログ
遅筋と毛細血管
2019/06/22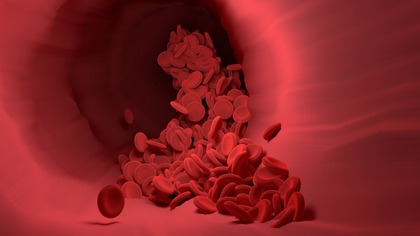
冷えと筋肉の関係の続きです。昨日は身体を温めるには筋肉が必要だけれどもその筋肉にも種類があるという話でした。おおまかに分けると筋肉は遅筋と速筋に分類できます。(本当は速筋はさらに2種類に分類されています。)
筋肉によって体内では熱が産生されますが、その熱を身体の隅々にまで届けるのは血液、血液が流れるのは血管です。
血液を運ぶ血管を増やすことは血行促進につながるのですが、遅筋の周りには毛細血管が多く速筋の周りには少ないのです。遅筋を鍛えることでその周りの毛細血管が増えてきます。
筋肉量が多い人でもジムで高重量のウェイトを扱っている筋肉隆々の人などは寒さに弱い場合があります。逆に一見細身で筋肉がなさそうでも遅筋がしっかり鍛えられている人の血行は良かったりするのです。(遅筋は鍛えても大して太くなりません。)
ヨガは基本的に呼吸を続けながらゆっくり動くので有酸素運動の要素が強くなります。ですので遅筋を鍛えやすい。ところどころで瞬間的な力が必要な箇所では速筋も使いますが、動き続けるための持久力が必要なので遅筋に近い特性を持った速筋が増えていくのだと思います。
遺伝的に速筋線維の割合が多い僕からすると、ヨガで行う持久力を伴うゆっくりした動きは「苦手」なものなのです。ですが苦手なゆっくりな動きは身体のバランスを整え体調も大幅に改善しました。その中には血行促進による冷えの改善も含まれます。今では長くアーサナをキープするのも心地よいくらいです。ヨガを始めた当時はじっとキープするのが辛くてしょうがなかったです。
特に特殊なスポーツや仕事に携わっているわけではない場合には、遅筋を鍛えることに注目した方が体調を維持、改善するには有効なのではないでしょうか。
冷え性などでお悩みの方は特に呼吸を止めずにじっくりゆっくり動くことをこころがけてヨガを行ってみてください。もちろん冷えにはホルモンや自律神経の働きなども絡んでくるとは思いますが、毛細血管が増えることはそれらの要素の改善にも繋がると思います。
ということでヒラメではなくマグロを目指しましょう。(ヒラメ的なスポーツや仕事をしている人はヒラメのままでいいと思います。)
遅筋と速筋
2019/06/21
昨日の続き、冷えに関してです。
寒さに強いか否かには複数の要因が絡んでいるとは思いますが、その中でも特に筋肉の影響はかなりあると思います。身体の筋肉量が多いか少ないかは冷えに関わります。さらには筋肉の種類が関わってきます。
今回のテーマはタイトルにあるように、
遅筋と速筋。
遅筋は瞬間的に大きな力は発揮できませんが、有酸素運動をする時に使われる持久力に特化した筋肉。周りに毛細血管も多く赤い筋肉(=赤筋)とも呼ばれます。(赤色は遅筋に多く含まれるミオグロビンというタンパク質の色)魚でも長時間遊泳する持久力型のマグロは赤身です。
速筋は短距離走などの無酸素運動の際に使われる筋肉。短い時間で大きな力を発揮する時に使われます。白い筋肉(=白筋)とも呼ばれます。魚では普段じっとしていて必要な時だけ素早く動くヒラメにはこのタイプの筋肉が多いです。白身魚ですね。
この間にピンク筋とも呼ばれる中間型の筋肉もあるのですが、ここではわかりやすく遅筋と速筋の2種類だけの話をします。
この遅筋と速筋は全ての人が身体の中にどちらも持っています。筋肉によっても遅筋が多いかか速筋が多いかの傾向は異なります。(例えば同じふくらはぎの筋肉でもヒラメ筋は遅筋の割合が多く、腓腹筋は速筋繊維が多いです。ただ上に述べた魚のヒラメは速筋中心ですのでヒラメ筋と混同しないようにしてくださいね。)
この遅筋と速筋の割合は人によって生まれつきの傾向が異なるのです。遺伝子によってそれは決まります。今の時代は便利で7000円程で検査キットを取り寄せて簡単に検査することができます。気になる方はネットで「スポーツ遺伝子」などと検索してみてください。
この検査では自分が、
速筋型
中間型
遅筋型
のどれに属するのかを調べることができます。それによって持久力系のものが向いてるのか瞬発力系のものが得意なのかなど自分の傾向を把握できたりします。まあでもこの遺伝子の他にも様々な要因が存在しますので、あくまで目安の傾向ですが。ほとんどの方が中間型ですしね。
ちなみに僕は速筋型です。
肝心の冷えと筋肉の種類の関係については長くなってしまうのでまた明日に持ち越します。
明日の朝のアナトミック骨盤ヨガでは遅筋(赤筋)を中心に鍛えていきます。
冷え
2019/06/20
今日は蒸していて暑いですね。歩くだけで汗をかきます。こんな日ですが「冷え」に関することを書きます。
先週の金曜日にとある都立高校の水泳部の指導に行ってきました。その水泳部の顧問の先生は昔僕が通っていた高校でも水泳部の顧問をしていた方でした。その先生からの頼みでここ3年ほど、たまに水泳部の練習を見に行っています。
高校生が水泳を頑張っている話はいずれ書くかもしれませんが、今日のテーマ別、「冷え」です。高校の外プールはこの時期とにかく寒いのです。
先週の金曜日は雨も降らず気温もそれなりに高かったのですが、それでも高校プールの水温は22℃くらい。普段プールに入らない方は、「なんだ、20℃以上あるならたいしたことないじゃん」と思うかもしれませんが、この水温は氷水に入っているような感覚です。普通の温水プールはだいたい31℃前後に水温を調整してありますので、それよりも10℃近く低いのです。
僕が水に入ったのは練習時間の最後の15分だけなのですが、体は縮こまって鳥肌が立ち、声が震えてきました。筋肉の動きも悪くなるので泳ぎも若干ぎこちなくなります。プールから上がった後もどっと疲れが出てしまいました。
ここで改めて思い出したのが自分は寒さに弱いということ。まあ22℃のプールなんて誰が入っても寒いのですが、周りの人の身体反応などを見てみると僕は明らかに寒さが苦手なようです。
これはなぜでしょう?人によって寒さに対する耐性が違うのは何が原因なのでしょうか?
色々と要因があるとは思いますが、あるポイントに絞って考えてみたいと思います。長くなってしまいそうなので続きはまた明日書いていこうと思います。
それではまた。
骨盤前傾
2019/06/08
今日は最近のブログのテーマになっている話はお休みにして、土曜日の朝のアナトミック骨盤ヨガについてです。
このヨガクラスはヨガの治療的側面を色濃く出した内容になっています。特に足の付け根を引き込んで骨盤を前に倒す動きを徹底的に行います。最初はよく感覚がわからないかもしれませんが、前傾姿勢を保っている時は腰を丸めないようにまっすぐ保ちます(というよりも元々ある腰の反りを保ちます)。この骨盤を前傾させる方向に力をかけられるようになってくると脚の付け根から熱くなり全身を温めます。この熱が筋肉の質を上げるのにも脂肪を燃焼するのにも役立ってきます。
ヨガでも様々な動きの要素がありますが、まずは騙されたと思ってこの骨盤を前傾させる動きを練習してみてください。
ところで先日、レッスンの参加者から、アナトミック骨盤ヨガでやるような骨盤前傾のアーサナはテレビで観るプロテニス選手の構えとそっくりだと言われました。
それは全くその通りで、サーブを受ける側の選手の構えは中腰で膝を開き、上半身は前傾させ腰を伸ばした状態を保っています。また他にもスキージャンプの滑走姿勢や力士の立会いの構えなどは似ている形をとっています。
これらのスポーツではどれも次の瞬間に素早い反応と動きを必要とします。構えている時の骨盤の前傾がそれを可能にするのです。(なぜ可能なのか?はレッスン時に少しずつ説明していこうと思います。)
ともかく様々なスポーツでも取り入れられているようなこの動きは、アスリートでなくても役立ちます。日常の姿勢を安定させ、動作を効率よくさせる。安定性と可動性のバランスも整えます。
そして6月からは金曜日の午前のクラスもアナトミック骨盤ヨガになりました。このクラスは土曜日のものよりもだいぶ運動強度を抑えています。体力的に不安がある方も安心できる内容となっていますのでぜひ一度お試しください。(むしろゆっくり動作を行うアナ骨は他のクラスよりも初心者向きと言えます。)
関連エントリー
-
 内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
-
 二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
-
 春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
-
 iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
-
 役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以
役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以










