RSYブログ
睡眠×不足×過多
2020/12/26
運動、栄養と来て今日は睡眠の話です。
睡眠の質はめちゃくちゃ大事なところではありますが、まずは細かい話は抜きにしてしっかり眠る時間を確保しましょう。
睡眠関連の本を何冊か読んでみると3〜4時間の睡眠で健康が維持できるショートスリーパー、10時間以上が必要なロングスリーパーはそれぞれ人口の1割くらいしかいません。しかもそれらはほとんど遺伝で決まるそうです。
なので大多数の方はミドルスリーパー。6〜9時間ほどの睡眠が必要なタイプです。その場合には睡眠時間が7時間を切ってくると日中のパフォーマンスが著しく低下します。
睡眠はその他の身体のケアなどでは代替できないのです。運動や栄養の面がしっかりしていても睡眠不足があるだけで心身は衰弱してしまいます。
睡眠時間をしっかりとるようにしただけで悩んでいた心身の不調が消えてしまうことがあります。働き過ぎで身体を壊すのもだいたいの場合睡眠不足が原因です。
ただ眠るのにも実は体力が必要なんですね。身体が弱り過ぎていると眠れば眠るほど疲れがたまるという現象も起きてきます。ここでも結局は運動と栄養との相互作用があるのです。運動や栄養が適切だと睡眠ホルモンのメラトニン(セロトニンから合成)もしっかり分泌されます。
まずは睡眠を中心に時間の使い方を見直すことで自分の日中の活動を密度の濃いものにできるのではないでしょうか。眠気と共に長い時間起きていることと比べるとその大切さがわかります。
あとはロングスリーパーでもないのに長過ぎる睡眠をとってしまうケースも要注意。身体のリズムが崩れて身体が重く、半分眠ったような生活に陥ってしまっているパターンです。適切な時間で疲れをとるにはやはり適度な運動から始めると改善します。
ヨガをやり始めたらぐっすり眠れるようになりました、ということもよく聞きます。睡眠には運動(呼吸法も運動の一種)が必要だし運動の回復には睡眠が必要なんですね。
いずれにしてもしっかりとした睡眠の量と質を確保するのが難しい時代。
「仕事があるから起きていなければならない」
「娯楽があるから起きていたい」
でも睡眠があってこそそれらをエネルギッシュに楽しむことができます。
みなさんは睡眠をサボっていませんか?
栄養×不足×過多
2020/12/25
昨日のブログでは運動について書きましたが今日は栄養です。
たくさん食べていても栄養が不足するというのは盲点かもしれませんね。現代版の脚気とでもいうべき症状は割と頻繁に起こるのです。
運動・栄養・睡眠の3つはどれも欠かせない要素でありお互いに作用し合ってます。特に運動をしっかりした後はこの栄養の補給が欠かせません。そして注意しなければならないのがその内容なのです。
昨日は「トレーニングすると筋肉に細かい傷がつきますよ」なんて話をしましたが、その傷を直すために栄養が必須になります。例えば体内で作り出せない必須アミノ酸、たんぱく質の代謝に関わるビタミンB6、体内の様々な代謝に関わるマグネシウムや亜鉛などのミネラルが不足するとトレーニングのダメージから回復することができません。
また体内でエネルギーを作り出す際にもビタミンB群やマグネシウムなどのミネラルが必要になります。不足すると動いたり考えたりするためのエネルギーがなくなり元気がなくなってしまいます。
結局体内ではこの身体を維持するための化学反応が常に起きているわけです。化学反応には材料が必要で、その材料が各種栄養素。体内で起こる物質の分解や合成を「代謝」と呼びます。
そして栄養の不足と過剰は隣り合わせ。
例えば三大栄養素の糖質を過剰に摂ると、糖質代謝に関わるビタミンB1などの栄養が余計に使われてしまいます。多量栄養素(糖質・脂質・タンパク質)を大量に摂ることで微量栄養素(ビタミン・ミネラル等)が逆に不足してしまうのですね。
エンプティフード(微量栄養素がほぼ皆無の食べ物)ばかり食べているとエネルギー代謝が回せなくなり鬱などの精神症状が出てしまうのはそのためです。糖質ばかり摂っていては体内の微量栄養素が足りなくなってしまいます。(体内で合成されるビタミンもありますがすぐに追いつかなくなってしまいます。)
現代生活はエンプティフードで溢れているので注意が必要です。菓子パンなども安くて気軽に買えますしね。ホールフード(食材丸ごとorそれに近い形)を自分で料理するのが身体には負担をかけません。
あとは糖質の質(GI値やその他の要素)や脂質の質(身体に有用な脂質)なども工夫するだけでだいぶ身体は変わりますがブログで散々触れてきたのでここでは省略します。
栄養は運動をたくさんする人、そして運動を全くしてない人は特に気をつけたい所。若い頃は栄養が不足していても細胞の若さでなんとかなることが多いですが、30代を過ぎた頃から食事内容による差がだんだん出てくるようです。
20代の頃に比べて最近なんだかエネルギーがないと感じる方は栄養について考え直すことで解決することもあると思います。
やりすぎ×やらなさすぎ
2020/12/23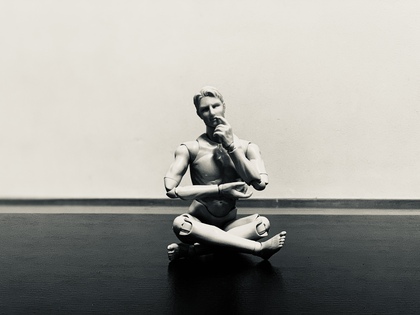
心身を元気にするには運動、栄養、睡眠(休養)が基本になります。どれが欠けてもどれが行き過ぎても不調が出てきます。
運動不足だと身体が重くなったり、やる気が出なかったり。
運動過多だと身体のあちこちに障害が出たり、常に疲労していたり。
栄養不足だと身体の材料が作れなかったり、鬱になったり。
余計な栄養過多だと肥満になったり脳の働きが鈍ったり。
睡眠不足だととにかく全てのパフォーマンスが下がったり。
睡眠過多だと筋力や脳が弱り何もする気が起きなくなったり。
特に今年のようなストレスがかかる状況下ではこの3つのバランスが崩れやすく心身が弱る人も多いと思います。
「運動・栄養・睡眠が身体にいいですよ。」なんていうのは誰でも知ってる話。でも本当にそれぞれがどれくらいの影響を心身に与えるかを知っている人は一握りもいないでしょう。
心身の不調に悩まされながらも身体にとって一番基本的で大事な要素を完全に無視してる人はたくさんいます。
明日からはその辺りの基本的な話をまた改めてしていければいいなと思います。(急に真面目なモード。)
速筋型の宿命
2020/12/06
気がついたらこのブログも毎日連続600投稿を超えていました。習慣化してしまえば続くものですね。何かを続ける持久力はついてきたようです。
しかしながらこのブログでも何度もお伝えしているように僕の筋肉は瞬発力型の白い筋肉(速筋)の割合が圧倒的に高いのです。持久力向きの赤い筋肉(遅筋)と瞬発力向きの白い筋肉(速筋)の割合は生まれつきの遺伝子にかなり左右されます。細かい説明は省きますがその遺伝子はRR型、RX型、XX型というタイプに分けられ、僕はRR型で速筋の割合が多いタイプ。
速筋タイプはここぞという時に爆発力をだせるので個人的には気に入ってはいるのですが遅筋繊維の割合が少ないことによるデメリットも当然あります。
特に苦労するのは冬。
寒さに弱いのです。
もちろん寒さに強いかどうかは他の要因も多く関わっているので筋肉のタイプどうこうで決まるものではないですが、遅筋か速筋かのくくりで言えば遅筋が多い方が寒さに強いです。(まあ体脂肪の量などの方が大きな要因になるかもしれませんが。)
遅筋の方が熱産生能力が高く、筋繊維の周りに毛細血管が多いのです。
僕もヨガを始めて遅筋も増え、それに伴い毛細血管も増えたのでしょうが、やはり冬は寒く血行が滞りがち。
もう少し遅筋を強化したいものです。
RR型(瞬発力型)の人に朗報なのは、トレーニングのやり方次第で持久力の方はかなり増やしていけるということ。逆にXX型(持久力型)の人が瞬発力を目に見えて増やすのには多大な労力が必要となります。
僕もアナ骨をコツコツやっていたらだいぶ持久力が増えてきました。
どんなタイプであれ生活に役立つ遅筋は強化出来ますので、みなさんも時間をしっかりかけてアーサナをやってみてくださいね。
身体を守る力
2020/12/03
人によって身体のリミッターというものはだいぶ異なります。リミッターとは自分が発揮する力に制限をかける安全装置のようなもの。瞬間的な力を発揮したいような時には邪魔だと感じることもあるかもしれませんが自分の心身を守るためには欠かせないものです。
例えばヨガクラスに参加してくれているAさんはこのリミッターの力が強いです。それゆえにアナ骨では長くキープできずにすぐにポーズを解いてしまったりします。しかしリミッターがうまく効いているため自分の力のラインが本能的にわかっています。休むのが非常に上手いのです。
昨日も風邪を引いたようなのにしっかりぐっすり休んでもう今朝のクラスには参加していました。自律神経の切り替えも上手です。眠りも深いと言っていました。まあこれはリミッター云々というよりも自己防衛能力が高いということになりますが。
逆に僕はこのリミッターが若干壊れかけたような状態になっているので大きな力は発揮できますが、かなり気をつけないと身体に必要以上の負荷をかけてしまいます。(ヨガを始めてからだいぶまともになりましたが。)僕からするとAさんのリミッターは喉から手が出るほど(出ないですが)欲しいものなのです。
リミッターが完全に外れた状態というのがいわゆる「火事場の馬鹿力」というやつですね。普通の主婦が車を持ち上げられると言います。まあこれは本当の緊急事態の話。
ちょっと色々な話の要素が混ざってしまいましたが、ともかく「どこまでやるのかやらないのか?」「どこまでできるのかできないのか?」にはものすごく個人差があるということ。
自分の特性を把握していきたいものですね。
引き算の大切さ
2020/12/01
生活習慣を少し変えるだけで身体が変わる余地はありますよ、なんて話を先日のブログでしました。例えば今まで運動習慣がなかった人が運動を始めたら10年前よりも動ける肉体になるという話。
やっていなかったことを始めたら心身に作用があるという「足し算」の話でした。
今日はその逆の「引き算」についてです。
生活習慣を変えるには主に二通りの方法があります。
やっていなかったことを始める「足し算」。
やってきたことをやめる「引き算」。
良いと思うことを始めるのはもちろん大切だと思うのですが、それ以上に心身が変化するのは自分にとって悪いもの、疑問に感じるものをやめることです。
特に依存しているものをやめると心身が全く変わります。(ものによっては一時的に離脱症状が強く出ますが。)
お酒、薬、タバコ、甘いもの、コーヒー、恋人、ゲームなどなど依存しやすいものはたくさんありますが、ドーパミンの過剰分泌などで毎日やめられない場合はかなりの体力と精神力をそのものに奪われてしまっています。
あとは、自分で疑問に思うような仕事や対人関係なども心と身体を疲れさせます。
自分の生活を思い浮かべてみてそういったものがもしあればやめてみると身体がスッキリして別物のようになると思います。(依存している場合はすぐにやめられないので徐々に減らしたり、専門的なやり方が必要になることが多いです。)
「引き算」ができると体力的、時間的、精神的な余地ができるので新しいことを始める「足し算」もやりやすくなります。
どんなにいい「足し算」でもやり過ぎると一つのことに集中できなくなってくるのでやっぱりまず「引き算」。
かなり人生のパフォーマンスが上がりますよ。
関連エントリー
-
 内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
-
 二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
-
 春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
-
 iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
-
 役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以
役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以










