RSYブログ
姿勢
2019/07/13
この前の日曜日のレッスン後に参加者の女性がこんなことを言っていました。
「最近自分の身体に目を向けるようになって姿勢が気になるんですけど、何が良い姿勢なのかわからないんです。」
どんな姿勢がベストなのか⁇確かに考えると難しいですよね。
姿勢と言えば多くの方がイメージするのが背骨の傾きかもしれません。猫背だったり背中が丸かったり、逆にまっすぐだったり。普段身体のことを意識している方が考えるのは骨盤の傾きや股関節のつき方だったりするのかもしれません。
色々な要素が積み重なってその人の立ち姿や座り姿をつくっているので、一口に「姿勢」と言っても難しいのですね。なので「この姿勢が一番いい姿勢」と決めつけてその姿勢をとるように努力するのは少々危ないことかもしれません。他人にとっての良い姿勢と自分にとっての良い姿勢は違うかもしれないし、同じ自分においても今と3年後の良い姿勢は変わっていたりします。
姿勢は筋肉や靭帯などがお互いに引き合って骨を安定させ自然に決まってきます。もし今自分が悪い姿勢だと思うなら何かしらの原因、例えば、ある部分の筋力不足、柔軟性不足、筋膜の拘縮などがあります。原因となる部分が改善すれば、骨格を支える力も蘇り自然に姿勢は身体が心地よいと思う方向へ変化します。
ヨガではそれらの原因を取り除き自分本来の姿勢を身体に思い出させる効果があります。もちろんそうなるためにはアーサナや呼吸をしっかりと行えるようになる必要はあるのですが。
まあでも「良い姿勢は身体が元々知っています。」なんて言ってもなかなかわかりづらいものだと思います。なので今朝のレッスンの最初の部分では、「解剖学的位置」というのを利用して参加者の方に自分の姿勢を体感してもらいました。
それについてはまた明日。
遅筋と毛細血管
2019/06/22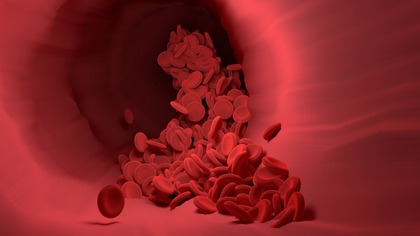
冷えと筋肉の関係の続きです。昨日は身体を温めるには筋肉が必要だけれどもその筋肉にも種類があるという話でした。おおまかに分けると筋肉は遅筋と速筋に分類できます。(本当は速筋はさらに2種類に分類されています。)
筋肉によって体内では熱が産生されますが、その熱を身体の隅々にまで届けるのは血液、血液が流れるのは血管です。
血液を運ぶ血管を増やすことは血行促進につながるのですが、遅筋の周りには毛細血管が多く速筋の周りには少ないのです。遅筋を鍛えることでその周りの毛細血管が増えてきます。
筋肉量が多い人でもジムで高重量のウェイトを扱っている筋肉隆々の人などは寒さに弱い場合があります。逆に一見細身で筋肉がなさそうでも遅筋がしっかり鍛えられている人の血行は良かったりするのです。(遅筋は鍛えても大して太くなりません。)
ヨガは基本的に呼吸を続けながらゆっくり動くので有酸素運動の要素が強くなります。ですので遅筋を鍛えやすい。ところどころで瞬間的な力が必要な箇所では速筋も使いますが、動き続けるための持久力が必要なので遅筋に近い特性を持った速筋が増えていくのだと思います。
遺伝的に速筋線維の割合が多い僕からすると、ヨガで行う持久力を伴うゆっくりした動きは「苦手」なものなのです。ですが苦手なゆっくりな動きは身体のバランスを整え体調も大幅に改善しました。その中には血行促進による冷えの改善も含まれます。今では長くアーサナをキープするのも心地よいくらいです。ヨガを始めた当時はじっとキープするのが辛くてしょうがなかったです。
特に特殊なスポーツや仕事に携わっているわけではない場合には、遅筋を鍛えることに注目した方が体調を維持、改善するには有効なのではないでしょうか。
冷え性などでお悩みの方は特に呼吸を止めずにじっくりゆっくり動くことをこころがけてヨガを行ってみてください。もちろん冷えにはホルモンや自律神経の働きなども絡んでくるとは思いますが、毛細血管が増えることはそれらの要素の改善にも繋がると思います。
ということでヒラメではなくマグロを目指しましょう。(ヒラメ的なスポーツや仕事をしている人はヒラメのままでいいと思います。)
遅筋と速筋
2019/06/21
昨日の続き、冷えに関してです。
寒さに強いか否かには複数の要因が絡んでいるとは思いますが、その中でも特に筋肉の影響はかなりあると思います。身体の筋肉量が多いか少ないかは冷えに関わります。さらには筋肉の種類が関わってきます。
今回のテーマはタイトルにあるように、
遅筋と速筋。
遅筋は瞬間的に大きな力は発揮できませんが、有酸素運動をする時に使われる持久力に特化した筋肉。周りに毛細血管も多く赤い筋肉(=赤筋)とも呼ばれます。(赤色は遅筋に多く含まれるミオグロビンというタンパク質の色)魚でも長時間遊泳する持久力型のマグロは赤身です。
速筋は短距離走などの無酸素運動の際に使われる筋肉。短い時間で大きな力を発揮する時に使われます。白い筋肉(=白筋)とも呼ばれます。魚では普段じっとしていて必要な時だけ素早く動くヒラメにはこのタイプの筋肉が多いです。白身魚ですね。
この間にピンク筋とも呼ばれる中間型の筋肉もあるのですが、ここではわかりやすく遅筋と速筋の2種類だけの話をします。
この遅筋と速筋は全ての人が身体の中にどちらも持っています。筋肉によっても遅筋が多いかか速筋が多いかの傾向は異なります。(例えば同じふくらはぎの筋肉でもヒラメ筋は遅筋の割合が多く、腓腹筋は速筋繊維が多いです。ただ上に述べた魚のヒラメは速筋中心ですのでヒラメ筋と混同しないようにしてくださいね。)
この遅筋と速筋の割合は人によって生まれつきの傾向が異なるのです。遺伝子によってそれは決まります。今の時代は便利で7000円程で検査キットを取り寄せて簡単に検査することができます。気になる方はネットで「スポーツ遺伝子」などと検索してみてください。
この検査では自分が、
速筋型
中間型
遅筋型
のどれに属するのかを調べることができます。それによって持久力系のものが向いてるのか瞬発力系のものが得意なのかなど自分の傾向を把握できたりします。まあでもこの遺伝子の他にも様々な要因が存在しますので、あくまで目安の傾向ですが。ほとんどの方が中間型ですしね。
ちなみに僕は速筋型です。
肝心の冷えと筋肉の種類の関係については長くなってしまうのでまた明日に持ち越します。
明日の朝のアナトミック骨盤ヨガでは遅筋(赤筋)を中心に鍛えていきます。
冷え
2019/06/20
今日は蒸していて暑いですね。歩くだけで汗をかきます。こんな日ですが「冷え」に関することを書きます。
先週の金曜日にとある都立高校の水泳部の指導に行ってきました。その水泳部の顧問の先生は昔僕が通っていた高校でも水泳部の顧問をしていた方でした。その先生からの頼みでここ3年ほど、たまに水泳部の練習を見に行っています。
高校生が水泳を頑張っている話はいずれ書くかもしれませんが、今日のテーマ別、「冷え」です。高校の外プールはこの時期とにかく寒いのです。
先週の金曜日は雨も降らず気温もそれなりに高かったのですが、それでも高校プールの水温は22℃くらい。普段プールに入らない方は、「なんだ、20℃以上あるならたいしたことないじゃん」と思うかもしれませんが、この水温は氷水に入っているような感覚です。普通の温水プールはだいたい31℃前後に水温を調整してありますので、それよりも10℃近く低いのです。
僕が水に入ったのは練習時間の最後の15分だけなのですが、体は縮こまって鳥肌が立ち、声が震えてきました。筋肉の動きも悪くなるので泳ぎも若干ぎこちなくなります。プールから上がった後もどっと疲れが出てしまいました。
ここで改めて思い出したのが自分は寒さに弱いということ。まあ22℃のプールなんて誰が入っても寒いのですが、周りの人の身体反応などを見てみると僕は明らかに寒さが苦手なようです。
これはなぜでしょう?人によって寒さに対する耐性が違うのは何が原因なのでしょうか?
色々と要因があるとは思いますが、あるポイントに絞って考えてみたいと思います。長くなってしまいそうなので続きはまた明日書いていこうと思います。
それではまた。
骨盤前傾
2019/06/08
今日は最近のブログのテーマになっている話はお休みにして、土曜日の朝のアナトミック骨盤ヨガについてです。
このヨガクラスはヨガの治療的側面を色濃く出した内容になっています。特に足の付け根を引き込んで骨盤を前に倒す動きを徹底的に行います。最初はよく感覚がわからないかもしれませんが、前傾姿勢を保っている時は腰を丸めないようにまっすぐ保ちます(というよりも元々ある腰の反りを保ちます)。この骨盤を前傾させる方向に力をかけられるようになってくると脚の付け根から熱くなり全身を温めます。この熱が筋肉の質を上げるのにも脂肪を燃焼するのにも役立ってきます。
ヨガでも様々な動きの要素がありますが、まずは騙されたと思ってこの骨盤を前傾させる動きを練習してみてください。
ところで先日、レッスンの参加者から、アナトミック骨盤ヨガでやるような骨盤前傾のアーサナはテレビで観るプロテニス選手の構えとそっくりだと言われました。
それは全くその通りで、サーブを受ける側の選手の構えは中腰で膝を開き、上半身は前傾させ腰を伸ばした状態を保っています。また他にもスキージャンプの滑走姿勢や力士の立会いの構えなどは似ている形をとっています。
これらのスポーツではどれも次の瞬間に素早い反応と動きを必要とします。構えている時の骨盤の前傾がそれを可能にするのです。(なぜ可能なのか?はレッスン時に少しずつ説明していこうと思います。)
ともかく様々なスポーツでも取り入れられているようなこの動きは、アスリートでなくても役立ちます。日常の姿勢を安定させ、動作を効率よくさせる。安定性と可動性のバランスも整えます。
そして6月からは金曜日の午前のクラスもアナトミック骨盤ヨガになりました。このクラスは土曜日のものよりもだいぶ運動強度を抑えています。体力的に不安がある方も安心できる内容となっていますのでぜひ一度お試しください。(むしろゆっくり動作を行うアナ骨は他のクラスよりも初心者向きと言えます。)
脂肪燃焼
2019/05/19
昨日のアナトミック骨盤ヨガ終了後に参加者の方からこんな質問がありました。
「お腹の肉はどうやって落ちますか?」
「お腹の肉」というのはお腹周りについた脂肪のことですが、この脂肪は分解されて身体の各部のエネルギー源にならないと減らないのです。脂肪が分解されたりエネルギーになるメカニズムはやや複雑なのでここでは説明しませんが、運動は当然脂肪燃焼を促進させます。特に有酸素運動は酸素を利用して脂肪を燃焼させていきます。ヨガも有酸素運動が主体となってきますので脂肪燃焼効果があります。
そしてもう一つ、脂肪を落とすには基礎代謝という概念が重要になってきます。基礎代謝とは生命を維持するために必要なエネルギーのこと。何もせずにじっとしていても内臓や脳やそして筋肉を維持するためにエネルギーが消費されています。一番簡単に基礎代謝量を増やす方法は筋肉を増やすこと。筋肉が増えるだけで何もせずに消費されるカロリーは増えていきます。
特に下半身の筋肉、太ももやお尻の筋肉は身体の中でも非常に大きく、これらの筋肉が増えることで基礎代謝量のアップが見込めます。何もしてない状況でも脂肪を燃やしやすい体質に変わってくるのです。
上記に加えてお腹周りが気になる場合には、腹横筋というコルセットのような筋肉を鍛えることも有効です。内臓の位置を保ったり腰を痛めないように保護する役割があります。お腹を引き締める効果があるので、ここが強化されると同じ量の脂肪がついていても腰のラインがすっきりして見えるようになります。吐く息とともにおへそを背骨のほうに引っ込めていくと鍛えられます。
お腹周りが気になる場合の対処法をまとめると、
1. 有酸素運動をする
2. 大きな筋肉をつけて基礎代謝を上げる
3. 腹横筋を中心にお腹周りの筋肉を鍛える
こうして見てみるとヨガはお腹周りが気になる場合にも効果が高いことがわかります。そして逆に痩せ過ぎで悩んでる方にも実は効果があるのです。その辺の話はまた今度機会があればしていこうと思います。
最近は暑くなってきましたので体調にはお気をつけてお過ごしください。
左右差
2019/05/07
だいぶ髪の毛が伸びてきたので今日は美容院に行ってきました。かなりさっぱりした感じになって家に帰って改めて髪型を見てみると、、
左右のもみあげの長さが全然違う…
長い方のもみあげを自分で短くしようとも思いましたが、どっちにしろ髪が伸びてくれば左右の差も埋まってくるのでそのままにすることにしました。
ところで髪型でなくとも身体には少なからず左右差があります。左右で脚の長さが違う、肩の位置が違う、目の大きさが違うなど人によってその度合いは違いますが完璧にシンメトリーな人はいないと思います。テニス選手の利き腕の太さや、漫画家の身体のねじれなど職業によってはかなりの左右差がでることも珍しくありません。
左右差自体あることが自然です。そもそも人間の内臓の位置関係は左右対称ではありません。肝臓は右側にあり、心臓は少し左寄りで胃も左から右に曲がっています。幼い頃に自然に利き手が決まることなどからも筋肉のバランスに差異が出てくるのは当然です。
差があって当然、しかし心臓などとは違って筋肉はほとんどが左右で対になっています。完全には同じ形にならないけど限りなく近い形でいようとする性質があります。
左右で違っていいのだけどあまりに差があり過ぎるとバランスを崩し不調をきたす。差が開き過ぎてしまった人は左右を整えていくことも身体を変えるための一つの手段です。
ヨガのアーサナを行っていると左右のバランスの違いに気づくことが多々あると思います。片足立ちのアーサナの差や、ヴィーラバドラーサナⅠの時の後ろ脚の付け根の固さの違いなど....僕も腸腰筋の固さの違いは相当あったのですがヨガを続けるうちに左右の柔軟性が近づいてきました。今も差はありますが依然よりも股関節が軽くバランスよく動くようになっています。
左右の差をあまり気にし過ぎず自分の身体を分析しながら淡々と身体を動かして行くのがいいのかなと今のところは思います。左右の差があることで身体のバランスを保っている部分もあるとも思いますしね。
「そもそも一つの身体を左右という枠組みでとらえたくない」という方はごめんなさい、僕も左右でとらえたいわけではありませんが、もみあげの長さが違ってしまったものでこんな話になってしまいました。身体のねじれなどについてはそのうち書こうと思います。
それでは。
アナトミック骨盤ヨガとお尻
2019/05/04
今日はRSYで初めてのアナトミック骨盤ヨガの日でしたが、レッスン後に参加された方からこんな声をいただきました。
「アナ骨でもお尻をかなり使ってる気がするし美尻をつくれるんじゃないか?」
そう、全くその通りでアナ骨でもお尻をたくさん使っていくのです。
アナ骨では股関節の屈曲の動きがたくさん出てきます。ローランジの前脚や、チェアポーズや四股を踏むようなアーサナで股関節の屈曲を強く使っています。そこからさらに大腿骨を骨盤方向へと引き込む力をかけていきます。この「引き込み」の話はまた次の機会に解説していきますが、今回はこれらのポーズでのお尻の働きに注目していきましょう。
お尻を形作る大きな筋肉である大臀筋の働きは主に股関節を伸展させることですが、上記のようなアーサナでは股関節を屈曲しているので大臀筋はストレッチされた状態になりますね。ストレッチと聞くと鍛える方向とは逆でお尻を強化する効果はないと思われるかもしれませんが、実はアナ骨にはものすごくお尻を鍛える作用もあるのです。
例えばチェアポーズやスクワットのような動きで後方にお尻を引く時に、臀筋は徐々に伸びて行きます。しかしただ伸ばされるわけではなく、筋肉が縮もうとしながら伸びて行くのです。ただ伸びてしまってはバランスを崩して転倒してしまうので、縮む力でブレーキをかけながらお尻が後方に引かれていきます。そしてアーサナの最終的な形まで到達した後のキープの時間では伸びる力と縮む力が釣り合った状態になります。このキープ時間中でも姿勢を崩さないように縮む力は常に働いています。
アナ骨では特にゆっくりとした動きでアーサナを行いますのでこのブレーキ動作やキープに長い時間をかけます。その間中ずっとお尻は縮もうとする力をかけ続けているのです。そしてブレーキ動作中はより筋肉に大きな負荷がかかり、結果的に筋肉の強化に繫がります。
アナ骨をやると脚の付け根とともにお尻に筋肉痛が起こりやすいのも上記のことが大きな理由になると思います。
お尻にも高い負荷をかけるアナ骨にも確かに「美尻」をつくる力はあると思います。
以上お尻の話でしたが、アナ骨の他の側面や効果についてはまたの機会にお伝えしていく予定です。
関連エントリー
-
 内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
-
 二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
-
 春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
-
 iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
-
 役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以
役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以










