RSYブログ
日常マインドフルネス
2020/10/26
最近は以前にも増して「今、この瞬間」に集中できているかに注意を向けています。
瞑想している時やアーサナの練習をしている時などはそういう意識が持ちやすいのですが、その他の日常生活ではなかなか自分の意識を「今ここ」に置いておくのが難しかったりするのです。もちろんどんな時でも1つのことに集中しなければならないというわけではありません。同時に物事を考えることが必要な時だってあります。
しかしよくよく自分の意識について観察してみると、多くの場面で注意力が散漫になっていたりするのです。インターネットで調べものをしている時に全然別のページを見ていたりとか。子ども達と遊んでいる時に仕事のことを考えていたりとか。どこか未来や過去、別の場所に心が飛んでいたりするのです。
まずは自分の集中がどこか別のことに逸れてしまっているなと気づくことが第一なのですが、そこまでできても今やっていることに完全に集中し直すのがなかなか難しい。しかし見つけました、良い方法。とある瞑想の本にはこんなことが載っていました。
注意が逸れてしまった時は目の前の物事に集中し直すのではなく、今行っている呼吸そのものに意識を向ける方が良い。
これめちゃくちゃいいです。だまされたと思って試してみてください。無理に今やっていることに意識を向けるのではなく、呼吸に集中するのです。お腹の動きや空気の流れなど何でもいいのです。そうすると、あら不思議!目の前のことに勝手に意識が向いてきます。もしまた別のことに意識が行ってしまったらまた呼吸に集中し直す、この繰り返しです。
こんなことを繰り返しているうちに集中力の土台が上がってきます。特に意識しなくても物事に集中しやすくなってきます。しかも心地良い感じの集中力。
ちょっとした意識の持ち方の違いなのですが抜群の効果。オススメです。
オキシトシン
2020/10/22
みなさんは誰かに愛情を感じていますか?今日は幸せや愛情といった感情を呼び起こすホルモンについての話です。
その名はオキシトシン。
オキシトシンの作用としては、
・抗ストレス作用
・幸福感を感じられる
・他人に愛情が湧く
などがあげられます。
普段イライラしたり、落ち込みやすい方に特に必要なホルモンになります。「愛情ホルモン」なんて呼ばれているようです。
さて、このオキシトシンがどのような時に大量に分泌されるかというと、
人と触れ合う時です。
スキンシップをしている時です。
配偶者や恋人がいる方はパートナーとスキンシップをとるだけでお互いに愛情ホルモンが分泌されます。パートナーがいない方は友達や知り合いと会話や食事を一緒にすると分泌されます。その際「楽しい時間を過ごす」というのがポイントになります。
また、犬などの動物と触れ合ってもオキシトシンは出るようです。アニマルセラピーでストレスが軽減するのもこのホルモンの効果が大きいのかもしれませんね。
いずれにしても家族や友達、動物などとスキンシップをしたり一緒に過ごす時間をとれるといいようです。
今年はコロナでそんな時間がかなり減ってしまったのではないかと思います。友達と食事にも行けない日々が続きました。今年のストレスレベルは相当なものなのではないでしょうか。やはり人間は他人と触れ合うことでバランスがとれる動物なのでしょうね。
とはいえ「旦那が在宅勤務でずっと家にいるのでストレスがハンパない。」という声も最近よく聞きます。スキンシップをとらないけど同じ空間にいるというのはすごいストレスなのですね。。逆にもっと近づいてスキンシップをとれればお互い愛情を感じることができるかもしれませんが。理解し合えずに共同生活をいうのが一番苦痛なのでしょう。
まあ上に書いたことも「楽しい時間」「愛情を感じる時間」というのが条件になると思うので、あまり仲が良くない夫婦などは無理せずに友達や動物などと触れ合うことでオキシトシン分泌を促しましょう。
ドーパミン
2020/10/21
今朝長男がトイレから出てきた後、妻にこう言いました。
「おかあちゃん、うんちにおしりがついてないかみてくれ。」
逆ですね…^^;
普段なかなかやる気が起きない方はドーパミンが不足している可能性があります。
ではどんな時にドーパミンが分泌されるかというと、
実際に自分で行動している時。
運動している時や仕事をどんどん片付けている時にドーパミンは分泌されます。
「いやいや、やる気が起きないのに行動するなんて無理だよ!」と言われてしまいそうですが、何も大きなことをしなくてもいいのです。例えば「この部屋だけ掃除してみよう」と思い、それを実行する。それだけでドーパミンの分泌が増し、その後の作業においてもやる気が出るようになります。
特に「それをやった後いいことがあるな」という期待感がある時により多くのドーパミンが分泌されるので、運動であれば運動後の爽快感や快感を覚えておけば、行動する以前から分泌が活発になります。行動の報酬を思い描くと出るのです。
あとはドーパミンのもとになるチロシンというアミノ酸を摂ることも有効なようです。大豆などに多く含まれるので普段から不足しないように摂っておくといいでしょう。やはりタンパク質は大事ですね。どのアミノ酸にもそれぞれの働きがあるのでバランスよく摂取できればいいと思います。
瞑想もドーパミンの分泌を促す効果があると言われています。確かに瞑想の後は高いやる気と集中力が続きますから神経伝達物質の分泌のバランスが変わるのでしょう。結局人生において瞑想というツールが最強な気がします。集中力、やる気、注意力、ストレス耐性、運動能力、イメージ力、創造力、全部上げますからね。
まあでもドーパミンは過剰になっても依存症(アルコール、ギャンブルなど)が起きてしまうので分泌が多ければ多いほど良いというわけではありません。昨日紹介したセロトニンにはドーパミンの暴走を防ぎ調整する機能があります。
なので太陽の光を十分に浴びつつ適度に運動や瞑想をしていれば、十分にやる気や集中力を発揮できる日々を過ごせるのではないでしょうか。
セロトニン
2020/10/20
今日は日差しが出て日中はかなり暖かくなりました。寒い時期になってくると日の光はありがたいですね。今日から何回かにわたって神経伝達物質を紹介しますが、初回は太陽光とも関係する物質です。
名前はセロトニン。
神経伝達物質の中でも1、2を争うほど有名人。
ほとんどが消化管に存在し、脳内にも存在する物質です。消化管では蠕動運動に関わる働きをするので不足すると便秘になったりします。
また脳内でのセロトニンは「幸せホルモン」と呼ばれるくらい感情への作用があります。気持ちを安定させたり、緊張感を和らげたり、一日のリズムを整えたり。また睡眠ホルモンのメラトニンの前駆物質でもあるので睡眠にも関わります。その役割は多岐に渡り不足すると以下のような症状が現れることがあります。
・イライラしやすくなる
・鬱傾向になる
・疲れやすくなる
・眠りが浅くなる。
・攻撃的になる
・パニックを起こしやすくなる
など。
さてそのセロトニンの分泌ですが少しコツがあります。以下のようなポイントをおさえられるといいかもしれません。
・太陽光を15~30分浴びる
・リズム運動をする
・セロトニンの原料になるトリプトファンを摂取する
一日のサイクルを整える上でも特に朝の光は大事になります。だから日照時間の短い冬や極端に日照時間の短い地域では鬱になる人が増加するんですよね。昔から太陽は崇められてきましたが人間の根本を整えるものなのです。
余裕があれば朝少し外でウォーキングしたりジョギングしたり、光の入る部屋でヨガをするのもいいですね。まさに太陽礼拝です。セロトニンを十分に分泌することで夜には先述のメラトニンに変換され深い睡眠もとれるようになります。
アミノ酸の一種であるトリプトファンはタンパク質の多いもの(肉、魚、大豆、卵など)には必ず入っているので極端に食事が偏らなければ大丈夫でしょう(本当は大丈夫という保証はないのですが詳しいことはまたそのうち)。バナナにも一定量のトリプトファンやビタミンB6が含まれているようです。(バナナは冷え体質の方は注意が必要ですが。)
朝の散歩などがハードルが高い場合には起き抜けにカーテンを開けて太陽光を少し浴びるだけでも違うと思います。
僕もウォーキングやジョギングはしないですが、朝長男を幼稚園に送っていく時に太陽の光を浴びながら自転車をこいでいるので、それがセロトニンの分泌に一役買っているんじゃないかなと思っています。
みなさんも自分の生活パターンに合わせて無理なくセロトニンを分泌してみてください!
オーディオブックが使える場面
2020/10/14
少し前にオーディオブックはなかなかオススメですよ、ということを書きましたが、今日はどんな点でオススメなのかを書いていこうと思います。
オーディオブックがオススメな状況というのは生活の中で多々あると思いますが、特に使えるなと思うのは、
新しい分野についての勉強を始めた時ではないかと思います。
今まで知らなかった分野の本というのは読むのがけっこう疲れます。まだ全体像を把握できていないのでページもなかなか進まないのです。知らない用語や概念も多いですからね。
そんな時にオーディオブックに読み聞かせをしてもらうのです。全部理解できなくても一冊読み切って全体像を把握します。できれば入門書よりもその分野について詳しく書いてあるものがいいと思います。そして1回で理解が乏しければもう一周する。とにかく概要を掴みます。
するとその後には同じ分野の本が格段に読みやすくなります。あとは何冊かその分野の本を読むor聴きさえすればその範囲の知識はかなり使えるようになります。
最初が一番労力が必要で大変なのでその部分をオーディオブックに任せてしまえば効率が上がります。
もちろん目があまり疲れない方や初めての分野もどんどん読み続けられる根気のある方は紙の本がいいと思いますが。(僕は目がすぐ疲れてしまいます^^;)
知らない分野になると極端に本を読むスピードが遅くなってしまう方にはオススメの方法です。
新しいことを始めるハードルがけっこう下がりますよ。
甘い物×甘い罠
2020/10/08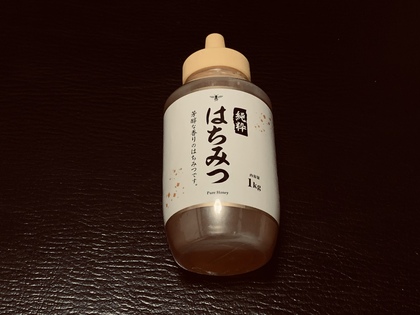
また食べ物関係の話。
うちでは子ども達に甘いお菓子をあまりたくさんあげないようにしています。するとけっこう幼稚園の親御さんからは驚かれるんですね。
なぜ驚くのでしょう?
僕たちの親やその上の世代の価値観の名残りなのかはわかりませんが、割と子ども=甘いものを食べるという図式が定着化しているように思います。
まあもちろん子どもは(大人も)甘いものを喜んで食べます。中毒性がありますからね。マイルドドラッグなんて呼ばれたりします。覚醒剤などより依存性は低いけど相当な依存性のあるもの。砂糖なんかはまさにそれです。
何かに依存する脳内の状態を作り出してしまうのも問題ですが、やはり血糖値の乱高下を起こしてしまうのは日常生活においてけっこうな問題だと思います。
甘いものを食べると一時的にハイになったり元気になりますが、すぐに血糖値が下がり集中力が切れたりイライラしたりします。(その甘いものに食物繊維などが含まれていれば血糖値の変化は多少穏やかになります。ほぼ砂糖やブドウ糖でできている飴玉やラムネは血糖調整においては負担になります。)
食べ物毎のG I値についてはネットで調べたりすれば表が出てきます。ただ反応には個人差があるので実際には自分で試してみなければわかりません。空腹時にその食べ物を食べてからだるさやイライラが出るまでの時間を比較します。(例えば同じ量の糖質を摂ったとしてもサツマイモとラムネでは子どもが不機嫌になるまでの時間が全然違います。)
まあだからと言っておやつにあげる甘いものをゼロにするのは難しいと思います。色々な物が溢れる今の時代にゼロを目指すと相当神経質にならなければならず、逆に変なストレスがかかりそうです。こんなこと書いている僕自身もたまにスニッカーズ(砂糖のかたまり)を食べることもあります。
正直大人に関しては自分の好きにすればいいと思います。自分の口にするものは自分の頭で決められますので。何かやりたいことがあって集中力や能力を上げたいならほどほどにした方がいいとは思いますが。
でもまだ知識も判断能力もない子どもの場合は要注意。
小さい子にタバコを吸わせる親はそんなにいるとは思えませんが子どもを砂糖漬けにしている親は相当多いと思われます。まあ体質的に何を食べても血糖値が安定していて依存症にならない子も一部いますけどね。糖分が切れただけですぐイライラしてしまう体質の子はそんな生活が何年も続くとけっこう厳しい所まで行きます。
子どもの能力で最近注目されているものに「非認知能力」というものがありますが、この能力にも摂り入れる栄養が深く関係しています。(非認知能力についてはまたの機会に。)
色々と書きましたが、なんのために口から物を入れるのか?という根本的な問いを立ててみると軸が定まるように思います。
例えばおやつに関してだったら、
・身体を成長させるための間食なのか?
・それとも脳の快楽のための嗜好品なのか?
・それは依存なのか?本当の悦びなのか?
などなど。
そういった問いの上でバランスをとっていけばいいのかと思います。
昔とは違いなんでも手に入る時代。(しかも身体に負担のかかるものの方が安くて準備も簡単。)口に入れるものでエネルギーを生み出したり身体を作る以上、多少の軸があった方が子どもにとっても良いのではないでしょうか。
縁側に腰掛ける
2020/10/03
今日のブログは京王線の電車の中で書いているのですが、久々に京王ライナーに当たりました。通常の電車として運行している京王ライナー。少しラッキーな気分です。いつもより一本遅い電車だからかな。。
さてタイトルの件ですが、昨日の午後は時間ができたので新スタジオになったengawayogaに修行に行ってきました。コロナ前と同じ目黒駅近くの建物。参加したクラスはBTY+T。BTYはBorn to Yog、Tはなんとタバタ式トレーニングのTでした。
タバタ式トレーニングは最近のブログ(HIIT)で紹介した4分間の高強度インターバルトレーニング。息子達と息を切らしながらやっているトレーニングです。ヨガとは真逆のような力の使い方をするのでかなりの刺激になります。
まあタバタは4分だけなのでそれ以外はBorn to Yog。逆転のポーズがとにかく多いクラスです。
engawayogaの先生のKiyoshiさんはヨガをやっている人の中でトップレベルに動ける方。昨年末くらいに一度Kiyoshiさんのクラスに参加したことがあり、今回は2回目でした。
自分の身体を成長させたい時には自分より動ける人のそばに行くのが一番です。昨日も間近でKiyoshiさんの動きを観察することで色々とヒントが得られました。おかげさまであまりバランスのとれなかった逆転のアーサナなども一気に安定しました。
一人で練習するのとは全然違いますね。成長したい時は刺激を受けられる人の元へ直行です。
動けるようになるのはどんな人にもメリットがあります。動けるようになるだけで感覚が研ぎ澄まされ集中力が増します。場合によっては物事への視野も広くなり、追究する心が生まれます。
みなさんは最近刺激を受けましたか?たまには強制的に自分を高めてくれる場所に行くのもいいですよ。(と自分に言い聞かせる。。)
パワーナップでパワーアップ
2020/10/01
みなさんは午後眠くなったりして集中力が落ちることはないですか?
食事の内容などで眠さをかなり抑えることはできますが、どうしても集中力が落ちてしまうことはあります。集中していれば10分で済むような作業も1時間かかってしまったり。。
そんな時にオススメなのがパワーナップです。
パワーナップとは20分前後の仮眠のこと。短いお昼寝です。
ポイントは長く寝過ぎないこと。30分以上眠ってしまうと段階がある睡眠のステージが上がってしまい、起きた後も眠気や怠さが残ってしまいます。パワーナップは15〜20分、どんなに長くても30分に抑えておきましょう。長く寝過ぎてしまうとかえって身体に良くないこともあります。
短い睡眠をとった後は気分がスッキリして集中力が回復します。起きた後に軽く身体を動かすなどしておくと更に作業能率が上がると思います。
夜の睡眠時間や質を確保するのはもちろんのこと、日中の睡眠の取り方でも生活の質が変わります。
仕事や家事がどうにも捗らない方、身体や頭を酷使している方、ぜひ一度お試しください^ ^
関連エントリー
-
 内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
内野と外野
小学校低学年〜中学年がやりたい球技No.1といえばドッジボールですが、うちの息子たちも例に漏れずハマっています
-
 二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
二代(台)目
このブログで度々書いているのですが、僕の中でのボディケアの最強マシンといえば、マッサージガン。ほぼ毎晩寝る前に
-
 春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
春の訪れと拒食明け
だんだんと暖かくなってきました。春の訪れを感じるようになってきたわけですが、我が家ではもう少し明確な指標でそれ
-
 iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
iZoo
一昨日は家族で日帰り旅行。iZooへ行って参りました。なんと9年ぶり。前回行った時には長男しか存在していません
-
 役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以
役職決め
事後報告で聞いた話なのですが、今朝僕がオンラインクラスを進めている間に家族会議が行われていたらしいのです。僕以










